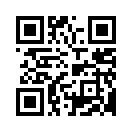2006年01月30日
沖縄報告108 チャーギ探偵団
沖縄報告、中村家住宅に来たというのに、庭木の中にチャーギ(イヌマキ)を探して、うろうろしている。
↓右の奥の木、あやしくない?

もっと大きくなると、こうなる。
あ。玉グスクにあったような気が・・・

うーん・・・これだけじゃわかんないな。
ところで、これが日本一のイヌマキなのだそうだ。
樹齢500年で13メートル、か。
500年前(1506年)といえば・・・
1504年:立河原の戦い
1506年:九頭竜川の戦い
1506年:般若野の戦い
1508年:撰銭の法
1510年:三浦の乱
1510年:沖縄全域が琉球王朝の領土となる
1510年:権現山の戦い
1512年:壬申約条締結
こんな時代(ムラウチ社長日記による)
もう少しで琉球全土(とはいえ島々はまだだが)が王朝の版図となる時代。
イヌマキ、こうなるとすごいね。
巨樹のもつ、荒々しい生命力、神々しい存在感が際立っている。
がじゅまるのように髭根はないけれど、キジムナーが住んでいそうだ。
暴れん坊のデイゴについて書いたけれど、それでも人々がデイゴを愛してきたのは、ただ花の美しさだけによるのではないのではないか?
樹木のもつ、時に荒々しいほどの生命力を身近な場所で感ずることによって、その「力」を吸収したいという想いがあったように感ずる。
そしてそれはまた、もっとわかりやすく言えば、「信仰の対象」ということであった。
チャーギが神に捧げられる(「なんくる主婦の年中わーばぐち」参照)のも、そういう精神的背景からではないかと、現時点でぼくは理解している。
もうひとつ、これはヤマト的解釈なのだけれど、葉が針や剣のような樹木は、魔除けとして用いられる。
じっさい、手裏剣の玩具にしたそうだ。
イヌマキの場合も、魔除けという目的が考えられるのだ。
それらが寺社に多く植えられているのも、このこととかかわりあうのかもしれない。
「イヌマキ 魔除け」で検索していたら・・・
薩摩(知覧)に屏風石(つまり、ヒンプン)を見つけてしまった。
中国では「土松(トゥーソン)」と呼ぶらしい。
それから、「羅漢松」というのも、もともとは中国語なのだった。
「袈裟」の形が、日本のお坊さんには似ていないと思ったぞ。
中国語の発音で「ルオ ハン ソン」。
・・・チャーギ探偵団、まだまだ奥は深そうだ。
↓右の奥の木、あやしくない?

もっと大きくなると、こうなる。
あ。玉グスクにあったような気が・・・

うーん・・・これだけじゃわかんないな。
ところで、これが日本一のイヌマキなのだそうだ。
樹齢500年で13メートル、か。
500年前(1506年)といえば・・・
1504年:立河原の戦い
1506年:九頭竜川の戦い
1506年:般若野の戦い
1508年:撰銭の法
1510年:三浦の乱
1510年:沖縄全域が琉球王朝の領土となる
1510年:権現山の戦い
1512年:壬申約条締結
こんな時代(ムラウチ社長日記による)
もう少しで琉球全土(とはいえ島々はまだだが)が王朝の版図となる時代。
イヌマキ、こうなるとすごいね。
巨樹のもつ、荒々しい生命力、神々しい存在感が際立っている。
がじゅまるのように髭根はないけれど、キジムナーが住んでいそうだ。
暴れん坊のデイゴについて書いたけれど、それでも人々がデイゴを愛してきたのは、ただ花の美しさだけによるのではないのではないか?
樹木のもつ、時に荒々しいほどの生命力を身近な場所で感ずることによって、その「力」を吸収したいという想いがあったように感ずる。
そしてそれはまた、もっとわかりやすく言えば、「信仰の対象」ということであった。
チャーギが神に捧げられる(「なんくる主婦の年中わーばぐち」参照)のも、そういう精神的背景からではないかと、現時点でぼくは理解している。
もうひとつ、これはヤマト的解釈なのだけれど、葉が針や剣のような樹木は、魔除けとして用いられる。
じっさい、手裏剣の玩具にしたそうだ。
イヌマキの場合も、魔除けという目的が考えられるのだ。
それらが寺社に多く植えられているのも、このこととかかわりあうのかもしれない。
「イヌマキ 魔除け」で検索していたら・・・
薩摩(知覧)に屏風石(つまり、ヒンプン)を見つけてしまった。
中国では「土松(トゥーソン)」と呼ぶらしい。
それから、「羅漢松」というのも、もともとは中国語なのだった。
「袈裟」の形が、日本のお坊さんには似ていないと思ったぞ。
中国語の発音で「ルオ ハン ソン」。
・・・チャーギ探偵団、まだまだ奥は深そうだ。
Posted by び ん at 08:15│Comments(0)
│沖縄報告0506
お返事が遅くなる場合があります。あしからず。