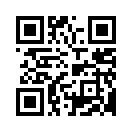2006年01月28日
沖縄報告107 イヌマキの巻
大晦日なので、とりあえず沖縄報告108までいっとこか、と思ったのだが・・・
あわてたのか、調子わるいのか、記事2つ消した(涙)
無理しても仕方ない。・・・のんびりいきましょう。

チャーギはイヌマキの別名(沖縄地域での呼び名)と知った。
名称につく「イヌ」というのは、役に立たないとか、似て非なるものとか、マイナスイメージで用いられる。
犬死だとか、犬侍だとか、犬桜(桜より見劣りするから)とかね。
ひどいけど。それが長い間のイメージだったのだからしかたない。
イヌマキ。ほんとうは、与論島が分布の最南端だったようだ。
それが、いまでは沖縄のあちこちで見かけられる。ことえに、その有用性のゆえだろう。
ちなみに、分布の最北が関東南部らしい。だから、暖かい地方の樹木ではあったのだ。
実は食用になるという。で、建材・器具・箱桶などに用いられ、庭園や生垣にされる、と。
古くは「羅漢松」(ラカンショウ)と呼んだという(『日本国語大辞典』)
江戸時代の薬学書『大和本草(やまとほんぞう)』から引用する(多少文字を改変した)。
杉をまきというに対して、羅漢松は犬まきという。
今は、ただ「まき」と称す。(略)
犬まきの木、その実、大にして小指のごとく、長くして人の形に似て、僧の袈裟かけたるがごとし。
ゆえに羅漢松の名あり。
実の色、赤・黄なり。
つまり、その実が、お坊さんが袈裟(けさ)をかけているように見えるから、羅漢松と呼んだのだそうだ。
これ・・・どうだろう?似てるかな。
あ。こうなると(右の)、似てるかもしれない(^〇^)
おー。たしかに、「実の色、赤・黄なり」であるな。
そうそう。画像の木、イヌマキだと思うんだけど、どうでしょう?(中村家住宅にて)
あわてたのか、調子わるいのか、記事2つ消した(涙)
無理しても仕方ない。・・・のんびりいきましょう。

チャーギはイヌマキの別名(沖縄地域での呼び名)と知った。
名称につく「イヌ」というのは、役に立たないとか、似て非なるものとか、マイナスイメージで用いられる。
犬死だとか、犬侍だとか、犬桜(桜より見劣りするから)とかね。
ひどいけど。それが長い間のイメージだったのだからしかたない。
イヌマキ。ほんとうは、与論島が分布の最南端だったようだ。
それが、いまでは沖縄のあちこちで見かけられる。ことえに、その有用性のゆえだろう。
ちなみに、分布の最北が関東南部らしい。だから、暖かい地方の樹木ではあったのだ。
実は食用になるという。で、建材・器具・箱桶などに用いられ、庭園や生垣にされる、と。
古くは「羅漢松」(ラカンショウ)と呼んだという(『日本国語大辞典』)
江戸時代の薬学書『大和本草(やまとほんぞう)』から引用する(多少文字を改変した)。
杉をまきというに対して、羅漢松は犬まきという。
今は、ただ「まき」と称す。(略)
犬まきの木、その実、大にして小指のごとく、長くして人の形に似て、僧の袈裟かけたるがごとし。
ゆえに羅漢松の名あり。
実の色、赤・黄なり。
つまり、その実が、お坊さんが袈裟(けさ)をかけているように見えるから、羅漢松と呼んだのだそうだ。
これ・・・どうだろう?似てるかな。
あ。こうなると(右の)、似てるかもしれない(^〇^)
おー。たしかに、「実の色、赤・黄なり」であるな。
そうそう。画像の木、イヌマキだと思うんだけど、どうでしょう?(中村家住宅にて)
Posted by び ん at 21:15│Comments(0)
│沖縄報告0506
お返事が遅くなる場合があります。あしからず。