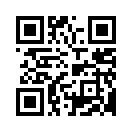2021年07月08日
那覇市100年に捧げる。(那覇の日に)
5月20日の那覇市市政100周年について、
(もう、1か月以上も過ぎてしまいましたけれども)、
ずっとスルーしたままだったことを思い出し、少し書きます。
「那覇の日」を逃したら、またいつになるかわからないので。
沖縄(本島)に行くには那覇市を避けて通ることはできません。
もし、那覇市を通らずに行こうと思うと、かなり大変なことになります。
与論島まで行って、そこから船に乗ると、フェリーで2930円。
とはいえ、そもそも飛行機で与論島まで、かなりかかりますよね。
ざっと、片道35000円というところですか。う~む・・・高額です。
(参照:skyscanner)

(2016年6月22日 与論島)
あるいは鹿児島から那覇港行きのマリックスラインに乗って、
本部港で降りるとか。そうすると鹿児島から本部港まで、
片道で大人13930円ほどかかるようですけれども。
(参照:マリックスラインHP)
ちなみに新大阪から鹿児島中央まで新幹線で21780円。
で、最短3時間46分で行けるんですか?そいつはびっくり。
もう、リニアなんていらないじゃないですか。いやほんまに。
本部や与論まで3万5千円という時点で十分高額すぎますが、
(地元の方は優待を受けられても、それでも高いですよね。)
費用を度外視するならば、チャーター便という方法もありますね。
セスナとか、どこか島から船を出してもらうとか、サバニで渡るとか。
・・・だんだん妄想がひどくなってくるので、このくらいで話を戻します。

(2017年9月5日 本部町)
つまり、何を言いたいのかといえば・・・
那覇空港を経由する限り、ぼくらは那覇市に必ず立ち寄る。
それだけ、那覇市にはお世話になって来たということになります。
ということで、話は「那覇市市政100周年」へとやってくるわけです。
いやはや、今回もまた、ほんとうにひさしぶりに書くので、
どういうふうに書いていいのか、かなり困っていますが、
那覇市100周年を祝っていることは間違いがなく。
ここからは、ぼくなりに、那覇市へのエールを。
もちろん、那覇市のホームページ、見せてもらっています。
(参照:那覇市公式ホームページ「市制100周年記念事業」)
那覇市100周年記念マグカップ(限定100個!)とか、
オリジナルフレーム切手とか、見事に転売されてますけど。
まあ、そういうのは自分で勝手にプリントするからいいとしても、
(もちろん売買はしませんよ。自分ひとりで楽しむための目的で。)
「1921年って何の年?」沖縄デジタル映像祭2020 CM部門
は、あまりにも閲覧数少なすぎるだろ!とツッコミを入れたり。
(企業賞の作品は好きです。後半、もうちょっと尺を確保して、
ひとりだけにボカシを入れなくてもいい動画に差し替えて、
ナレーターだけは申しわけないけどちゃんとした人雇って。)
そんなこんなで、100周年記念誌の『那覇100年の物語』は、
期待しておきたいなと思っているのです。買いに行けるまで。
編集はボーダーインクなので、間違いはないと思っています。
(参照:沖縄タイムス+プラス2021年5月16日 11:00 )
世の中には、ネット販売ってものがあるのですけども・笑
まあ、いいんです。「行くための理由」がひとつでも増えれば。

(2018年9月7日 那覇空港)
那覇市の人口が近年減少していることは、なんとなく、
耳にはしていました。当初は半信半疑でしたけれども。
なんといっても、お隣の豊見城市の発展が、ものすごい。
ここ10年以上、日本中の市町村の中での人口増加率で、
2年に1回くらいの割合で全国1位に選ばれているはずです。

(2017年6月24日 豊見城市)
われわれ観光客にとっても、豊見城市の比重は、
近年ますます、どんどん大きくなっています。
レンタカーに乗り込むのはたいてい豊見城からですし。
レンタカーに乗って最初の食事か、特に返す前の食事は、
渋滞を避けたいので、那覇より豊見城でのことが多くなった。
そんなこともあり、かねて耳にする移住人口のこともあって、
もし、那覇市の人口が経りつつあるのだとしても、
沖縄県の人口は、まだ増え続けていると思っていたのです。。

(同上)
ところが、最新の人口統計によれば、
これがじつは、減っているのですね。
沖縄県の人口。・・・知りませんでした。
いわゆる「移住ブーム」に乗った8割の人たちは、
すでに沖縄にはいないとも聞いていますけれど。
そのような統計は公的には存在しないはずなので、
「体感」や、「ざっくり」の数字で「8割」なのでしょう。
そうなんだ・・・大変なことも多いのだなと思います。
「好き」だけでは、なかなかむずかしいのでしょうか。
かつて移住を思い詰めた者として身につまされます。
もともと4月は人口流動が大きいので、県外流出人口も多く、
しかし、そのぶん3月から4月にかけてやってくる人も多くて、
一時的に増減の幅が大きくなったとしても、結局は人口増に、
振れていたわけですが、それが現在、確実に減少している。
ただし、人口動態の確定数が出ているのは2年前までなので、
まだ不確定な部分は残っているといえば、残っているのです。
しかし、それでも減少が増加に転じるほど微妙な数ではない。
つまり、どう考えても2年前から県人口は減り続けている。
総務省統計局の2018年から2019年にかけての人口増は、
約2000人、正確には全県で2393人にとどまっています。
143万2千人が143万4千人になっているだけなのです。
中でも那覇市は、2393人の内16人の自然増にとどまる。
(自然増というのは、出生数から死亡数を引いた数です。)
そして、県人口は2019年から2020年にかけて、
ほぼ横ばいになり(つまり、2019年にピークがあり)、
2020年から今年にかけて、ついに減少を始めています。
(各市町村の動態を集計すれば、確実に減少を始めます。)
それでも、人口増加を続けている地域はもちろんあって、
どこが増えているのかと言えば、那覇市の周辺市域。
中部では宜野湾・コザ・うるまの3市で計1000人を超え、
南部では糸満・豊見城と、浦添を合わせて計1000人を超える。
つまり、全県の自然増の9割が、この6市に集中しているのです。

(浦添市内から宜野湾市の嘉数高台公園を 2017.6.22)
従来の、沖縄県の人口増の最大の理由は出生数が多かったこと。
「復帰」2年後の1974年から人口当たりの出生数は日本一ですし、
これは、今後も変わる気配はありません(少なくとも、しばらくは)。
それでも、人口の増加率は毎年5%以上減り続けています。
沖縄県保健医療部保健医療総務課が、昨年10月に発表した、
2019年の「 沖縄県人口動態統計(確定数)の概況」によれば、
たとえば25年前の1986年に、自然増は17を超えていました。
1年で、1000人当たり17人以上が増えていたことになります。
ところが、2019年は、その値が10分の1になって1.7。
1年間で、1000人当たり2人以下しか増えていません。
それも、前の年の2.5から一気に減っての1.7です。
そしてこれは、コロナの影響を受ける以前の数字です。
転入の増加分が、自然減を受け止めきれなくなった・・・。
客観的・分析的にいえば、そういうことになります。
では、結婚する人の数が少なくなっているのかといえば、
19年の結婚数は8000組を超え、前年より140組も増加。
そして、離婚件数も、1組だけですけど、減っています。
つまり結婚が減り、離婚が増えたからではないのですね。
もうひとつ、統計資料を見て、ほっとする数字があります。
それは、1986年時点の乳幼児死亡率6.7という高さが、
(つまり、1000人当たりで7人近くも亡くなっていたのが)
5分の1以下の1.3まで、劇的に減少を続けてきたこと。
現今の医療機関逼迫のニュースには胸が痛くなりますが、
信頼に足る医療の進歩には、力づけられる思いです。
先日、沖縄県のコロナ感染状況を述べるコメンテーターが、
医療体制の脆弱さにすべての理由があるように述べていて、
ちょっと待てよ!と声に出して突っ込まざるをえなかったのですが、
そういう根拠のない発言は、じつにまったく恥ずかしい限りです。
沖縄県の人口当たり病院数と医師数はほぼ全国平均値、
そして、看護師数は全国平均の110%を超えていて、
病床数も全国平均値を大きく上回っているけれど、
診療所の数だけは、全国平均の約7割と低い。
そして、医療機関の大半が本島南部に集中していることで、
医療の「南北問題」が生じており、さらに島嶼部における、
医療体制の課題もなかなか解決されない現状にある。
ただ、それは日本全国どこでも言えることであって、
Dr.コトーを必要としているのは与那国だけじゃない。
県立病院中心の医療体制は沖縄の特殊事情ですが、
それもまた、沖縄県に責任があるわけでは決してない。
しいて言うならば、「復帰」以来の日本政府の責任ですし、
大学病院や私立病院の充実のみが医療レベルの高さではない。
(「充実」とは、わかりやすく言い換えれば「カネの注ぎ込み」ですね。)
沖縄の現状を見かねて、心ある医療従事者たちが、
日本全国から次々に沖縄に向かっている報道を見て、
(6月前半の時点で、100名を超えたと聞いています。)
いかにも沖縄の医療体制に問題があるように思うのは、
あまりにも短絡的で、浅薄な見方としか言いようがない。
そのくらいの常識は押さえてから発言すべきでしょう。
自分なら、そうします。ただ、民放は疲弊するだけなので、
テレビの出演は、10年ほど前から断わっていますけれど。
まあ、単に呼ばれなくなったというだけのことなのでしょう。
それでも、「朝ナマ」に呼ばれたら出ようとは思っていますが、
肝心の田原総一朗が、最近何を言っているのかわからない。
そういう自分自身も、結果的に根拠もなく信じていることが、
いくらだってあるので五十歩百歩といったところでしょうか。
(「エビデンス」という最近の流行言葉はほんとうに嫌いです。
エビがダンスしているようで落ち着かない・・・。まあ、そもそも、
そういう問題ではありませんが、エビフライは好きです )
)
沖縄県の人口は単純に150万を超えると思っていたので、
おそらく今年中に143万を割ってしまうという減少の速度に、
正直、おどろきと、かなり大きなとまどいを隠しきれません。
そのなかでも那覇市の減少傾向は群を抜いています。
もちろん昨年からはコロナの影響があるでしょうけれど、
それ以前から減少していたというのは、ショックです。
ぼくが住んでいる市は、4年前に市政50周年を迎え、
その前後に人口50万人を切って減り続けています。
最大値は52万人でさほど変化していないのですが、
それでも40年以上ずっと人口50万人超を続けて、
市役所をはじめとする各種施設をここ20年で一新し、
中核市になって、ラグビーのワールドカップを誘致し、
さてこれから、というところで、どっと減り始めました。
なので現在、人口動態に関しては手探り状態ですし、
何を根拠に今後を考えればいいのかが、わからない。
人口自然減のほかに、いろいろ理由はありますけれど、
(あると思いますが)まあそれは、ここでの話題ではなく、
「目の前の問題」として考えていきます。仕事なので。
(20年前までは「文学」が仕事だったはずなのですが、
いったい、いつからこうなったのか、よくわかりませんw)
ただ、外国人人口が増加して2万人を超えているので、
人口総数では減少幅がさほど目立たないのですね。
それでも、2030年には45万人と予測されていて、
(予測しているところもあって、が正解ですけれど、
あるいはそれ以上の減少があるかもしれない。)
あまりに急激な人口減に、とまどうばかりです。
同じことが那覇市で起こるとは思いませんけれど、
それでも、しばらく増え続けると思われた人口が、
大幅減少に転じたことは事実として間違いがない。
(その主要因が、周辺市域への流出、だとしても。)
現在の32万人が40年後に25万になると予想する、
那覇市自身の予測値(2016年)も存在しています。
参照:那覇市まち・ひと・しごと創生総合戦略 2016年5月)
「本市の将来推計人口は 2015 年から 2020 年にかけて人口のピークを迎え、その後は減少に転じ、2060 年代には、約 25 万 4 千人に減少することが推計されています。」

ちょうど5年前の推計ですが、先見の明には敬意を表します。
ぼくはその頃、那覇市の人口は、高層住宅が立ち並ぶことで、
35万に達するのではないかと、単純に予想していましたので。
日本国内というより、むしろ中国(特に上海)や香港の姿を見て、
(言うまでもなく香港からは流出が続いています。胸が痛みます。)
スペースがあれば都市部への人口集中は続くと思っていたのです。
実際、那覇市ほど新しく広いスペースが生まれた県庁所在地は、
日本では他に存在しませんでしたから。とりわけ21世紀に入って。

(「新しく広いスペース」としての、おもろまちにて 2018.6.24)
というわけで、「那覇市100年に捧ぐ」というタイトルをつけながら、
なんだかネガティヴな記事になってしまったようにも思います。
けれども、人口減というのは、ある意味でチャンスですよね。
人口増加局面の環境下では、なかなかできなかったことが、
可能性として、多面的に構想できるようになりますから。
つまりそれは、ひとりに当たる光が多くなるということ。
(ただ、光を当てるということ自体が不可能になってしまう、
たとえば限界集落のような極端な人口減少もありますから、
前向きに考えてばかりも、もちろんいられないのですが。)
現在、こうやって人の数を示す様々な数値を並べると、
どうしてもコロナ感染者数を思い浮かべてしまいます。
大阪では、感染者数は低くなっていっていますが、
それでも重傷者・死者の数は依然高い数値です。
(そもそも、人の命を数値で示すこと自体、
ものすごく抵抗を覚えていたことですけれど、
慣れていく自分がいて、ふと考え込みます。)
そして、いよいよ底を打って、じわりと増加が・・・。
沖縄県の感染関連の数値は高止まりしたまま、
小中高の一斉休校が、先月20日に終了しました。
いられても困るという家庭もあることは承知の上で、
ちゃんと家にいてくれよ、と心から思いましたが、
感染者数から見て、かなりがんばったようですね。
今や、この「がんばった」という言葉も嫌な言葉ですが。
日本全国で、沖縄県だけが緊急事態宣言の継続中ですが、
はたして、昨日・今日のニュースで取り上げられるまで、
どれだけの日本人がこのことを知っていたでしょうか?
おそらく沖縄県の緊急事態宣言は解除され、
まんえん防止措置に移行すると思いきや、
この後も緊急事態宣言が続くようですね。
あたかも東京との抱き合わせのように。
地域によってメリハリをつけるためという、
昨日までの沖縄県の説明は非常にわかりやすく、
なにひとつわかりやすく説明しない政府との差異が際立ちましたが、
1日たってみたら、緊急事態宣言続行ということで驚きました。
東京で、今出すべきものは、緊急事態宣言ではないでしょう?
それは、どう考えても、東京五輪中止の宣言であるはずです。

(国際通りを車中から 2018.6.23)
ニュースは、がらんとした国際通りばかりを映し、
その一方で乗客の減らない航空機の話題があり、
いったい、どれが「ほんとう」なんだ?・・・と思います。
きっと、どれも「ほんとう」なんだろうなとは思うのですが。
それでも、「切り取り方」によって、これほど変わる情報を、
じっさいに見に行くことができない状況に、わじわじ~します。
この、わじわじ~する気構えこそがクセモノだとは思うのですが、
こればかりは、じっさいにどうすることもできませんので。
ただ、大半の場所では、当たり前の日常が進んでいて、
そこにコロナ対策と小中高の休校が重なっていたのだと、
遠く思いを馳せるばかりだったのですけれど・・・。
それでも20歳未満の感染者が毎週倍増を続けるという、
5月からの状況は、ほんとうに大変なことだったと思います。
(過去形が妥当なのかどうか、これもわからないのですが。)
そして、それほどきびしい状況があるのにもかかわらず、
何ひとつ教訓にできず、目をつぶり耳をふさいだまま、
(自らの欲望と、甘美な夢想を見るために呆けたまま)
下劣で強欲至極な「五輪貴族の道楽」につきあって、
(おつきあいするフリで自分の利権だけは手放さず)
東京五輪という名の感染実験を止めることができない、
日本政府の狂気に身の毛がよだつ思いをしています。
せっかくのお祝い記事の最後がこうなりましたが、
この不条理に対しては、もっと声を上げ続けないと、
いけないと思っています。ほんとうに、ほんとうに。
それは決して感染状況がどうこうという話ではなく、
政府が国民をどれだけないがしろにするのかという、
国というものの根本理念にかかわる問題ですので。
そして、それこそは、「沖縄差別」の根幹と、
確実にからみついている構造問題なので。
少し前までは、この政権に殺されたくないと、
そう思って「がんばって」きましたが、今は、
「開催」という拠点を確保したその時点から、
どれほど不条理な無理強いが広がってゆくのか、
そのトンデモナイ行く先をこの目で確かめるため、
こんな中途半端な時点でまだ死ねないなと思っています。
ワクチン接種がいつになるのか、接種したとして変異株に、
どれだけ対応できるのかといったことは五里霧中ですが、
「市政100年の那覇」を、まだ見ていませんから、ね。
いつかまた沖縄に出かけることができるようになった時、
コロナのおかげで会えなくなっている人がいないでほしいと、
ブログは休んでばかりいても、そのことは祈っているのです。
(もう、1か月以上も過ぎてしまいましたけれども)、
ずっとスルーしたままだったことを思い出し、少し書きます。
「那覇の日」を逃したら、またいつになるかわからないので。
沖縄(本島)に行くには那覇市を避けて通ることはできません。
もし、那覇市を通らずに行こうと思うと、かなり大変なことになります。
与論島まで行って、そこから船に乗ると、フェリーで2930円。
とはいえ、そもそも飛行機で与論島まで、かなりかかりますよね。
ざっと、片道35000円というところですか。う~む・・・高額です。
(参照:skyscanner)
(2016年6月22日 与論島)
あるいは鹿児島から那覇港行きのマリックスラインに乗って、
本部港で降りるとか。そうすると鹿児島から本部港まで、
片道で大人13930円ほどかかるようですけれども。
(参照:マリックスラインHP)
ちなみに新大阪から鹿児島中央まで新幹線で21780円。
で、最短3時間46分で行けるんですか?そいつはびっくり。
もう、リニアなんていらないじゃないですか。いやほんまに。
本部や与論まで3万5千円という時点で十分高額すぎますが、
(地元の方は優待を受けられても、それでも高いですよね。)
費用を度外視するならば、チャーター便という方法もありますね。
セスナとか、どこか島から船を出してもらうとか、サバニで渡るとか。
・・・だんだん妄想がひどくなってくるので、このくらいで話を戻します。
(2017年9月5日 本部町)
つまり、何を言いたいのかといえば・・・
那覇空港を経由する限り、ぼくらは那覇市に必ず立ち寄る。
それだけ、那覇市にはお世話になって来たということになります。
ということで、話は「那覇市市政100周年」へとやってくるわけです。
いやはや、今回もまた、ほんとうにひさしぶりに書くので、
どういうふうに書いていいのか、かなり困っていますが、
那覇市100周年を祝っていることは間違いがなく。
ここからは、ぼくなりに、那覇市へのエールを。
もちろん、那覇市のホームページ、見せてもらっています。
(参照:那覇市公式ホームページ「市制100周年記念事業」)
那覇市100周年記念マグカップ(限定100個!)とか、
オリジナルフレーム切手とか、見事に転売されてますけど。
まあ、そういうのは自分で勝手にプリントするからいいとしても、
(もちろん売買はしませんよ。自分ひとりで楽しむための目的で。)
「1921年って何の年?」沖縄デジタル映像祭2020 CM部門
は、あまりにも閲覧数少なすぎるだろ!とツッコミを入れたり。
(企業賞の作品は好きです。後半、もうちょっと尺を確保して、
ひとりだけにボカシを入れなくてもいい動画に差し替えて、
ナレーターだけは申しわけないけどちゃんとした人雇って。)
そんなこんなで、100周年記念誌の『那覇100年の物語』は、
期待しておきたいなと思っているのです。買いに行けるまで。
編集はボーダーインクなので、間違いはないと思っています。
(参照:沖縄タイムス+プラス2021年5月16日 11:00 )
世の中には、ネット販売ってものがあるのですけども・笑
まあ、いいんです。「行くための理由」がひとつでも増えれば。
(2018年9月7日 那覇空港)
那覇市の人口が近年減少していることは、なんとなく、
耳にはしていました。当初は半信半疑でしたけれども。
なんといっても、お隣の豊見城市の発展が、ものすごい。
ここ10年以上、日本中の市町村の中での人口増加率で、
2年に1回くらいの割合で全国1位に選ばれているはずです。
(2017年6月24日 豊見城市)
われわれ観光客にとっても、豊見城市の比重は、
近年ますます、どんどん大きくなっています。
レンタカーに乗り込むのはたいてい豊見城からですし。
レンタカーに乗って最初の食事か、特に返す前の食事は、
渋滞を避けたいので、那覇より豊見城でのことが多くなった。
そんなこともあり、かねて耳にする移住人口のこともあって、
もし、那覇市の人口が経りつつあるのだとしても、
沖縄県の人口は、まだ増え続けていると思っていたのです。。
(同上)
ところが、最新の人口統計によれば、
これがじつは、減っているのですね。
沖縄県の人口。・・・知りませんでした。
いわゆる「移住ブーム」に乗った8割の人たちは、
すでに沖縄にはいないとも聞いていますけれど。
そのような統計は公的には存在しないはずなので、
「体感」や、「ざっくり」の数字で「8割」なのでしょう。
そうなんだ・・・大変なことも多いのだなと思います。
「好き」だけでは、なかなかむずかしいのでしょうか。
かつて移住を思い詰めた者として身につまされます。
もともと4月は人口流動が大きいので、県外流出人口も多く、
しかし、そのぶん3月から4月にかけてやってくる人も多くて、
一時的に増減の幅が大きくなったとしても、結局は人口増に、
振れていたわけですが、それが現在、確実に減少している。
ただし、人口動態の確定数が出ているのは2年前までなので、
まだ不確定な部分は残っているといえば、残っているのです。
しかし、それでも減少が増加に転じるほど微妙な数ではない。
つまり、どう考えても2年前から県人口は減り続けている。
総務省統計局の2018年から2019年にかけての人口増は、
約2000人、正確には全県で2393人にとどまっています。
143万2千人が143万4千人になっているだけなのです。
中でも那覇市は、2393人の内16人の自然増にとどまる。
(自然増というのは、出生数から死亡数を引いた数です。)
そして、県人口は2019年から2020年にかけて、
ほぼ横ばいになり(つまり、2019年にピークがあり)、
2020年から今年にかけて、ついに減少を始めています。
(各市町村の動態を集計すれば、確実に減少を始めます。)
それでも、人口増加を続けている地域はもちろんあって、
どこが増えているのかと言えば、那覇市の周辺市域。
中部では宜野湾・コザ・うるまの3市で計1000人を超え、
南部では糸満・豊見城と、浦添を合わせて計1000人を超える。
つまり、全県の自然増の9割が、この6市に集中しているのです。
(浦添市内から宜野湾市の嘉数高台公園を 2017.6.22)
従来の、沖縄県の人口増の最大の理由は出生数が多かったこと。
「復帰」2年後の1974年から人口当たりの出生数は日本一ですし、
これは、今後も変わる気配はありません(少なくとも、しばらくは)。
それでも、人口の増加率は毎年5%以上減り続けています。
沖縄県保健医療部保健医療総務課が、昨年10月に発表した、
2019年の「 沖縄県人口動態統計(確定数)の概況」によれば、
たとえば25年前の1986年に、自然増は17を超えていました。
1年で、1000人当たり17人以上が増えていたことになります。
ところが、2019年は、その値が10分の1になって1.7。
1年間で、1000人当たり2人以下しか増えていません。
それも、前の年の2.5から一気に減っての1.7です。
そしてこれは、コロナの影響を受ける以前の数字です。
転入の増加分が、自然減を受け止めきれなくなった・・・。
客観的・分析的にいえば、そういうことになります。
では、結婚する人の数が少なくなっているのかといえば、
19年の結婚数は8000組を超え、前年より140組も増加。
そして、離婚件数も、1組だけですけど、減っています。
つまり結婚が減り、離婚が増えたからではないのですね。
もうひとつ、統計資料を見て、ほっとする数字があります。
それは、1986年時点の乳幼児死亡率6.7という高さが、
(つまり、1000人当たりで7人近くも亡くなっていたのが)
5分の1以下の1.3まで、劇的に減少を続けてきたこと。
現今の医療機関逼迫のニュースには胸が痛くなりますが、
信頼に足る医療の進歩には、力づけられる思いです。
先日、沖縄県のコロナ感染状況を述べるコメンテーターが、
医療体制の脆弱さにすべての理由があるように述べていて、
ちょっと待てよ!と声に出して突っ込まざるをえなかったのですが、
そういう根拠のない発言は、じつにまったく恥ずかしい限りです。
沖縄県の人口当たり病院数と医師数はほぼ全国平均値、
そして、看護師数は全国平均の110%を超えていて、
病床数も全国平均値を大きく上回っているけれど、
診療所の数だけは、全国平均の約7割と低い。
そして、医療機関の大半が本島南部に集中していることで、
医療の「南北問題」が生じており、さらに島嶼部における、
医療体制の課題もなかなか解決されない現状にある。
ただ、それは日本全国どこでも言えることであって、
Dr.コトーを必要としているのは与那国だけじゃない。
県立病院中心の医療体制は沖縄の特殊事情ですが、
それもまた、沖縄県に責任があるわけでは決してない。
しいて言うならば、「復帰」以来の日本政府の責任ですし、
大学病院や私立病院の充実のみが医療レベルの高さではない。
(「充実」とは、わかりやすく言い換えれば「カネの注ぎ込み」ですね。)
沖縄の現状を見かねて、心ある医療従事者たちが、
日本全国から次々に沖縄に向かっている報道を見て、
(6月前半の時点で、100名を超えたと聞いています。)
いかにも沖縄の医療体制に問題があるように思うのは、
あまりにも短絡的で、浅薄な見方としか言いようがない。
そのくらいの常識は押さえてから発言すべきでしょう。
自分なら、そうします。ただ、民放は疲弊するだけなので、
テレビの出演は、10年ほど前から断わっていますけれど。
まあ、単に呼ばれなくなったというだけのことなのでしょう。
それでも、「朝ナマ」に呼ばれたら出ようとは思っていますが、
肝心の田原総一朗が、最近何を言っているのかわからない。
そういう自分自身も、結果的に根拠もなく信じていることが、
いくらだってあるので五十歩百歩といったところでしょうか。
(「エビデンス」という最近の流行言葉はほんとうに嫌いです。
エビがダンスしているようで落ち着かない・・・。まあ、そもそも、
そういう問題ではありませんが、エビフライは好きです
 )
)沖縄県の人口は単純に150万を超えると思っていたので、
おそらく今年中に143万を割ってしまうという減少の速度に、
正直、おどろきと、かなり大きなとまどいを隠しきれません。
そのなかでも那覇市の減少傾向は群を抜いています。
もちろん昨年からはコロナの影響があるでしょうけれど、
それ以前から減少していたというのは、ショックです。
ぼくが住んでいる市は、4年前に市政50周年を迎え、
その前後に人口50万人を切って減り続けています。
最大値は52万人でさほど変化していないのですが、
それでも40年以上ずっと人口50万人超を続けて、
市役所をはじめとする各種施設をここ20年で一新し、
中核市になって、ラグビーのワールドカップを誘致し、
さてこれから、というところで、どっと減り始めました。
なので現在、人口動態に関しては手探り状態ですし、
何を根拠に今後を考えればいいのかが、わからない。
人口自然減のほかに、いろいろ理由はありますけれど、
(あると思いますが)まあそれは、ここでの話題ではなく、
「目の前の問題」として考えていきます。仕事なので。
(20年前までは「文学」が仕事だったはずなのですが、
いったい、いつからこうなったのか、よくわかりませんw)
ただ、外国人人口が増加して2万人を超えているので、
人口総数では減少幅がさほど目立たないのですね。
それでも、2030年には45万人と予測されていて、
(予測しているところもあって、が正解ですけれど、
あるいはそれ以上の減少があるかもしれない。)
あまりに急激な人口減に、とまどうばかりです。
同じことが那覇市で起こるとは思いませんけれど、
それでも、しばらく増え続けると思われた人口が、
大幅減少に転じたことは事実として間違いがない。
(その主要因が、周辺市域への流出、だとしても。)
現在の32万人が40年後に25万になると予想する、
那覇市自身の予測値(2016年)も存在しています。
参照:那覇市まち・ひと・しごと創生総合戦略 2016年5月)
「本市の将来推計人口は 2015 年から 2020 年にかけて人口のピークを迎え、その後は減少に転じ、2060 年代には、約 25 万 4 千人に減少することが推計されています。」

ちょうど5年前の推計ですが、先見の明には敬意を表します。
ぼくはその頃、那覇市の人口は、高層住宅が立ち並ぶことで、
35万に達するのではないかと、単純に予想していましたので。
日本国内というより、むしろ中国(特に上海)や香港の姿を見て、
(言うまでもなく香港からは流出が続いています。胸が痛みます。)
スペースがあれば都市部への人口集中は続くと思っていたのです。
実際、那覇市ほど新しく広いスペースが生まれた県庁所在地は、
日本では他に存在しませんでしたから。とりわけ21世紀に入って。
(「新しく広いスペース」としての、おもろまちにて 2018.6.24)
というわけで、「那覇市100年に捧ぐ」というタイトルをつけながら、
なんだかネガティヴな記事になってしまったようにも思います。
けれども、人口減というのは、ある意味でチャンスですよね。
人口増加局面の環境下では、なかなかできなかったことが、
可能性として、多面的に構想できるようになりますから。
つまりそれは、ひとりに当たる光が多くなるということ。
(ただ、光を当てるということ自体が不可能になってしまう、
たとえば限界集落のような極端な人口減少もありますから、
前向きに考えてばかりも、もちろんいられないのですが。)
現在、こうやって人の数を示す様々な数値を並べると、
どうしてもコロナ感染者数を思い浮かべてしまいます。
大阪では、感染者数は低くなっていっていますが、
それでも重傷者・死者の数は依然高い数値です。
(そもそも、人の命を数値で示すこと自体、
ものすごく抵抗を覚えていたことですけれど、
慣れていく自分がいて、ふと考え込みます。)
そして、いよいよ底を打って、じわりと増加が・・・。
沖縄県の感染関連の数値は高止まりしたまま、
小中高の一斉休校が、先月20日に終了しました。
いられても困るという家庭もあることは承知の上で、
ちゃんと家にいてくれよ、と心から思いましたが、
感染者数から見て、かなりがんばったようですね。
今や、この「がんばった」という言葉も嫌な言葉ですが。
日本全国で、沖縄県だけが緊急事態宣言の継続中ですが、
はたして、昨日・今日のニュースで取り上げられるまで、
どれだけの日本人がこのことを知っていたでしょうか?
おそらく沖縄県の緊急事態宣言は解除され、
まんえん防止措置に移行すると思いきや、
この後も緊急事態宣言が続くようですね。
あたかも東京との抱き合わせのように。
地域によってメリハリをつけるためという、
昨日までの沖縄県の説明は非常にわかりやすく、
なにひとつわかりやすく説明しない政府との差異が際立ちましたが、
1日たってみたら、緊急事態宣言続行ということで驚きました。
東京で、今出すべきものは、緊急事態宣言ではないでしょう?
それは、どう考えても、東京五輪中止の宣言であるはずです。
(国際通りを車中から 2018.6.23)
ニュースは、がらんとした国際通りばかりを映し、
その一方で乗客の減らない航空機の話題があり、
いったい、どれが「ほんとう」なんだ?・・・と思います。
きっと、どれも「ほんとう」なんだろうなとは思うのですが。
それでも、「切り取り方」によって、これほど変わる情報を、
じっさいに見に行くことができない状況に、わじわじ~します。
この、わじわじ~する気構えこそがクセモノだとは思うのですが、
こればかりは、じっさいにどうすることもできませんので。
ただ、大半の場所では、当たり前の日常が進んでいて、
そこにコロナ対策と小中高の休校が重なっていたのだと、
遠く思いを馳せるばかりだったのですけれど・・・。
それでも20歳未満の感染者が毎週倍増を続けるという、
5月からの状況は、ほんとうに大変なことだったと思います。
(過去形が妥当なのかどうか、これもわからないのですが。)
そして、それほどきびしい状況があるのにもかかわらず、
何ひとつ教訓にできず、目をつぶり耳をふさいだまま、
(自らの欲望と、甘美な夢想を見るために呆けたまま)
下劣で強欲至極な「五輪貴族の道楽」につきあって、
(おつきあいするフリで自分の利権だけは手放さず)
東京五輪という名の感染実験を止めることができない、
日本政府の狂気に身の毛がよだつ思いをしています。
せっかくのお祝い記事の最後がこうなりましたが、
この不条理に対しては、もっと声を上げ続けないと、
いけないと思っています。ほんとうに、ほんとうに。
それは決して感染状況がどうこうという話ではなく、
政府が国民をどれだけないがしろにするのかという、
国というものの根本理念にかかわる問題ですので。
そして、それこそは、「沖縄差別」の根幹と、
確実にからみついている構造問題なので。
少し前までは、この政権に殺されたくないと、
そう思って「がんばって」きましたが、今は、
「開催」という拠点を確保したその時点から、
どれほど不条理な無理強いが広がってゆくのか、
そのトンデモナイ行く先をこの目で確かめるため、
こんな中途半端な時点でまだ死ねないなと思っています。
ワクチン接種がいつになるのか、接種したとして変異株に、
どれだけ対応できるのかといったことは五里霧中ですが、
「市政100年の那覇」を、まだ見ていませんから、ね。
いつかまた沖縄に出かけることができるようになった時、
コロナのおかげで会えなくなっている人がいないでほしいと、
ブログは休んでばかりいても、そのことは祈っているのです。
この記事へのコメント
久しぶりに来てみました。
沖縄県の人口統計の分析に只々頷いております。
これだけの分析力にまだまだ健在の様子は嬉しく思います。
コロナ禍は五輪といい五里霧中は続きそうですね。
今!都会の一極集中の人口密度もありますが、私が一番危惧するのは
島の閉塞感からくる過疎化ですかね、(八重山、宮古、古宇利島除く)
田舎や島取材をしながら限界集落からくるコミュニテイーが成り立つのか心配です。
番組の「ポツンと一軒家」は人生模様があり好きでみておりますが、これからの日本のあり方を考えますと、かなり危機的な状況ではと思ってしまします。とはいえ心配してもしょうないのですが、独り言を書きこんでしまいました。
沖縄県の人口統計の分析に只々頷いております。
これだけの分析力にまだまだ健在の様子は嬉しく思います。
コロナ禍は五輪といい五里霧中は続きそうですね。
今!都会の一極集中の人口密度もありますが、私が一番危惧するのは
島の閉塞感からくる過疎化ですかね、(八重山、宮古、古宇利島除く)
田舎や島取材をしながら限界集落からくるコミュニテイーが成り立つのか心配です。
番組の「ポツンと一軒家」は人生模様があり好きでみておりますが、これからの日本のあり方を考えますと、かなり危機的な状況ではと思ってしまします。とはいえ心配してもしょうないのですが、独り言を書きこんでしまいました。
Posted by サワフジ at 2021年07月15日 17:11
at 2021年07月15日 17:11
 at 2021年07月15日 17:11
at 2021年07月15日 17:11お褒めにあずかり、恐縮しています。一知半解の分析まがいですが、沖縄県人口の減少のことが気になっておりましたので。
「島の閉塞感からくる過疎化」に虚を突かれる思いです。八重山・宮古もさることながら、古宇利島という具体的な名が、他の有人等の状況を照らし出しているように切実に伝わってきました。
「鉄道が通れば」「交通機関さえ整備されれば」(過疎から解放される)と願っていた地域が、鉄道の開通とともに人がいなくなってしまう現象を「ストロー現象」と呼んでいますが、「橋が架かる」ということが同様に「人を吸い出してしまう」ことがあるのですね。
古宇利島は5年前に娘2人と行ったきりですが、観光客の群れが強く印象に残っています。「逆ストロー」の事例なのでしょうか。コロナ後の平穏が戻って来たならば、島歩きから始めたいと娘たちとも話していたところです。
時節柄くれぐれもご自愛ください。またお会いできる日を楽しみにしています。
「島の閉塞感からくる過疎化」に虚を突かれる思いです。八重山・宮古もさることながら、古宇利島という具体的な名が、他の有人等の状況を照らし出しているように切実に伝わってきました。
「鉄道が通れば」「交通機関さえ整備されれば」(過疎から解放される)と願っていた地域が、鉄道の開通とともに人がいなくなってしまう現象を「ストロー現象」と呼んでいますが、「橋が架かる」ということが同様に「人を吸い出してしまう」ことがあるのですね。
古宇利島は5年前に娘2人と行ったきりですが、観光客の群れが強く印象に残っています。「逆ストロー」の事例なのでしょうか。コロナ後の平穏が戻って来たならば、島歩きから始めたいと娘たちとも話していたところです。
時節柄くれぐれもご自愛ください。またお会いできる日を楽しみにしています。
Posted by び ん at 2021年07月16日 12:29
at 2021年07月16日 12:29
 at 2021年07月16日 12:29
at 2021年07月16日 12:29お返事が遅くなる場合があります。あしからず。