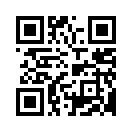2006年03月21日
かけがえのない場所
3月13日に沖縄から帰り、
3月16日に書いた記事(「斎場御嶽を荒らすのは誰だ!」)。
まだほとんど沖縄にいるような気分で
あつい余韻にひたりつつ書いた。
だから整理がついていないと言うつもりはない。
ただ、まだうまくまとまりがついていないことも事実なのだ。
5日後になっても、まだTBやコメントが届けられる。
ぼくの僅かな経験から言えば、これはめずらしい。
たいてい、その日と次の日くらいでコメントは止まる。
そして、あとから読んでくださった方が例外的にコメントをくださる。
一般的には、だいたい、そのようなかたちだ。
ところが、この記事は、そうではなかった。
5日たっても、まだコンスタントにTBやコメントが届けられるのだ。
それだけ、多くの人が持続的に関心を持っている問題なのだろう。
そしておそらく、しばらくの時間をおかないと語りにくかった問題でもあるのだろう。
試みに、記事別のアクセス数を見てみたら251。
100アクセスあれば多い方だという各記事の中で、突出している。
これまで「沖縄・八重山探偵団」で、記事別アクセス一覧の欄外に消えるまでで最も多いアクセスのあった記事では1100を超えたが、これは例外中の例外。
250というアクセス数が、この「事件」への静かでありながら強い関心を示している。
じっさいに、、てぃーだ内の他のブログでも真摯な意見が交換されている。
ぼくの知る限り、あゆさんの「沖縄文学館」に集約されたリストが最も詳細。
よって、ここでは、そちらをご参照いただきたいと記して、責を塞いでおく。

前置きが長くなった。
ぼくは本心では、斎場御嶽にせよ、中グスクにせよ、久高島の拝所にせよ、長い長い祈りの場として伝えてきた人々の手に、一元的に在るべきだと思う。
逆に言えば、いくら世界遺産というシルシつきの観光名所となったところで、それは不特定多数の人の「持ち物」ではないと考える。
あえて強い言い方をすれば、たとえば中グスクが立ち入り禁止になることで聖地としての機能を保持できるのであれば、そうすべきであると思うのだ。
話が拡散するので、先ずは今回自分の目で見、話を聞いてきた中グスクに絞りたい。
中グスクの聖木伐採には、いくつかの要素が絡み合っている。
そもそも4000㎡にも及ぶ中グスクエリアの、どの木が聖木で、どれがそうでないかという問題はおいて、たしかに、世界遺産指定以後に多くの木々が伐採されてきた。
地権者による伐採があったという。管理母体による伐採があった。そして、それらには(納得できるかできないかは別として)それぞれの理由があった。
いま、その詳細を述べることは控えておくが、「聖なる場所を破壊しよう」と考えて樹木の伐採をおこなった者は皆無だということだけをここでは述べておきたい。
他者の心の中に踏み込んでいけない部分があるように、この世界には踏み込んではならない領分というものがある。
その、本来踏み込んではならない領分に、不特定多数の人間が踏み込まざるをえない状況を作り出したことこそが、問題の核心であると考える。
つまり、世界遺産指定というかたちで、より多くの人間を受け入れるシステムの中に中グスクをはじめとする聖域(すくなくとも聖域を含んだエリア)を組み込んだ時点で、それは行政的管理の権限の中に組み込まれることを認めたということなのだ。
管理責任者の論理からすれば、エリア内に危険因子を残しておくことは出来ない。
よって、ハブの住み着く可能性のある草叢や潅木は除去される。風で枝が落ちる可能性のある高木もまた除去される。そして、見学者に危険を及ぼす可能性のある石垣は補強されなけらばならない。
そのような大状況の中で、「聖域であること」を条件に、危険因子を保持することは、すでに不可能なのだ。
たとえば、識名園では(ここも、今回赴いて確認してきたのだが)、園内にあった拝所は、開園整備の一環として園外へと移動させられている。
具体的には3つの(日本式に言えば)祠が、入口横の事務棟の背後へと移転されているのだ。
事務所で聞いた答えは、園内にあると拝みに来た人が入園料を払わないといけなくなるので、入園料のいらない場所に移転したのだということであった。
いきなり降り始めた土砂降りの中で聞いたその話には、愕然とした。
もちろん、古式に則ったかたちで移転はおこなわれたに違いない。
しかし、それが「管理する側の論理」なのだ。
考えるに、終戦後半世紀あまり、ほとんど廃墟であった識名園だから、
つまり、拝所としての機能をほとんど失っていた期間の長い場所だから、
このようなふるまいが可能となったのに違いあるまい。
しかし考えてみれば、斎場御嶽だとて、期間の長短はあれ、拝所としての機能をほぼ停止していた時期が無いわけではない。そのことは意識しておく必要があるように思う。
つまり、永劫の聖地という考え方は、万世一系という神話と同様、時に思考を硬化させる可能性があるということだ。
今回はじめて訪れて確認した、中グスクに匹敵するほどのグスク機能を備えた大里グスクが現在ほぼグスクとしての形態を失っている(復元の15年計画は始まっている)のに、拝所としての機能を保持していることに鑑みれば、中グスクもまた、同様に廃墟としての姿の中で拝所のみの時代があったことは明らかである。
しかし、である。そのような拝所としての機能・論理を現実的に超えたところで、世界遺産・観光資源という論理が組織されてしまった以上、聖地としての意味は下位価値としてその下に組み込まれざるをえない。
だからあきらめようと言っているのではない。「世界遺産」を錦の御旗のように振り回すことの是非を、再確認する場を持ちたいと思っている。
もちろん、ユネスコの果たしてきた役割を軽視しようというつもりはない。
しかし、1992年にユネスコ世界遺産センターができてから、わずか14年という歳月で、この構想に万全の信頼と期待を抱くべきではないとも思っている。
文化遺産と自然遺産、そして複合遺産をあわせて現在世界で800あまりが登録されている世界遺産。
しかし、文化・自然の保存という目的が逆に今回のように文化・自然の破壊につながることは、おそらく例外ではない。
現在、内地に10(本州に9、近畿地方に4)ある世界遺産指定の地域・文化財が、逆に指定を受けることでもたらした問題(多くは観光地化の強化による環境破壊)は、まだ真摯に総括されていない。
その意味で、現在はまだ世界遺産指定の是非を問う実験期間であると思うのだ。
であれば、その実験は審問されなければならない。より望ましい現実のために。
果たして、斎場御嶽が世界遺産登録を受けなければ、今回の盗難事件(それは3月9日から10日にかけてのことであったとされる)が発生しなかったかといえば、それは分からない。
すでに香炉の盗難はくり返しおこなわれてきたという情報もある。
また、同様に世界遺産指定を受けなければ中グスクの聖木伐採がなかったかといえば、どうであろう(種々の情報からは、中グスクにかんしては世界遺産指定が聖木伐採の主要因であったと考えられるのではあるが)
だから、世界遺産指定も、問題系のひとつの要因に過ぎないといえば過ぎないのだが、しかし連綿と続く「事件」の背景(本質)に、やはり世界遺産指定は大きく関与しているはずなのだ。

娘と一緒に、近くの公園を散歩してきた。
整備されたばかりの公園に、二つ並んで置かれたベンチが目に付いた。
このベンチが、人生におけるかけがえのない場所となる人が、きっといる。
その人にとってみれば、この「場」を落書きや破壊で汚されることは耐え難いことだろう。
しかしその一方で、この公園には管理母体(市)があり、ベンチは「その人」の持ち物ではない。
もちろんここは、聖地・拝所といった、歴史という「多くの人の思い」が折り重なった場所ではない。
しかし積分すれば、聖地とて、その場所を「かけがえのない」と思う人、思われた時間の集積によって聖地たりえている。
逆に微分すれば、どこであれ、その場所を「かけがえのない」と思う人思う意識があれば、そこは侵すべからざる場所であるに違いない。
わかりやすいのは、自分の家であり、自分の部屋である。
家や部屋で考えれば、何が侵害なのかという認識は大多数が共有している。
斎場御嶽の事件の場合、こがね壺や香炉を盗まれることによって誰が何を侵されているのかが見えない(見えにくい)状況の中に現代という社会が置かれている構造が露呈している。
だから、この事件を論じる多くの人(ぼくも含めて)が、問題は盗難事件そのものにあるのではなく、そのような事件を誘発するこの社会構造にあるのだと観じている。
しかし、とも思うのだ。
「ここ」は、ある人にとってかけがえのない場所に、別の人が土足で踏み込むことを奨励する社会。
つまりは、観光地であるとか世界遺産であるとかといったコンセプトのもとに、本来聖地である(そこを聖地であると認識する者しか踏み込めない)場所を不特定多数の人間に対してオープンにして行く(それどころか、有効な対策もなく次々に呼び込む)こと自体が、やはり大きな問題ではないだろうか。
世界遺産指定をはずすという選択肢。いささかの退嬰をこめて言うならば、それこそが斎場御嶽を、そして中グスクを救う、最大にして最短の近道と思うのだ。
それができないというのであれば、KUWAさんが逆説的に言われる、「柵と鎖でがんじがらめにした聖域」も仕方がないと感じている。
いまは、観光至上(つまるところ経済至上)のシステムの中に組み込まれた聖域の何を守ることが優先順位かを考えるべき時である。それが対症療法に過ぎないのであれ何であれ。
そもそも「心の中の善を喚起する」場であるはずの聖域に対する犯罪が続発するのである以上。
ただし、かんじがらめにすべき対象が、じつに多種多様であり、ある意味で聖域を守る役割の人の手を鎖で縛らなければ聖域が破壊されるという大いなる皮肉こそが、この問題の一筋縄では行かない大きな要素となっているのであるけれども。

聖地・聖域を考えることは、難しい。
そもそもその場所が「聖」なる要件を、共有することが必ずしも容易ではないからだ。
ある者にとってみれば侵すべからざる場所が、別の者にとってみれば易々と踏みにじりうる場所であるということは、この社会にはいくらでもある。
たとえばAにとって花園ラグビー場は、人生のすべてを賭けうる神聖な殿堂であるが、B(ぼくでもいい)にとってみれば子どもを遊ばす広場でしかない。
そのとき、なぜその場がAにとって神聖な場所であるかを伝達することがまず必要だ(ただし、Aの価値観の中では)
次に、その場所を侵すべからざる場所であるという価値観を共有させることが必要だ。
しかし、ぼくはべつに花園ラグビー場広場に入っても緊張もしないし、ありがたいとも思わない。
あえて言えば、ストーンサークル風のモニュメントに沈む夕日を見るのが好きというだけだ。
ただ、その場を「かけがえのない」と思う多くの人たちがいるということを、さざざまなメディアによって理解している。
だから(という「以前に、社会の一員として)ラグビー場に落書きをしないし、備品を盗もうとも思わない。
そこで、あえて強い言い方をすれば、花園ラグビー場と斎場御嶽の「聖度」に、どれだけの差異があるのか、ということになる。
その差異を、だれに向かって、どのように理解させるか、理解させうるかという話になるのではないか。
「理解させる」という言い方が高圧的であることは承知しつつ。
斎場御嶽の盗難事件に心を痛めるほどの人は、「自分の心の問題」として自らに厳しく自問する。
そしてその結果、(傾向性として言っているいのだが)精神を純化させつつ内向してゆく。
そのような純化された精神が、この世界に存在すること自体は、とても尊いことだ。
ただし、そのように内向化する尊い自問のかたわらで、実際に聖地は破壊され続けている。
ぼく自身「何が出来るか」という自問自答の中にいて、
しかし、やはり「何かをしたい」と考えている。
現在、このブログを訪れてくださる方は、日に300人ほど。
しかし、その300人が一同に会する場面を一旦想像してみれば、
それが、どれほどものすごい人数であるかが実感できる。
そこでぼくは先ず、その人たちに語りかけてみることにしよう。
あなたは、世界遺産登録後にくり返される、聖地の破壊について
どのような意見や感想をお持ちですか?
じつにまとまらぬ文章となったが、
引き続き考えたいと思っている。
ご意見をいただければ幸いである。
3月16日に書いた記事(「斎場御嶽を荒らすのは誰だ!」)。
まだほとんど沖縄にいるような気分で
あつい余韻にひたりつつ書いた。
だから整理がついていないと言うつもりはない。
ただ、まだうまくまとまりがついていないことも事実なのだ。
5日後になっても、まだTBやコメントが届けられる。
ぼくの僅かな経験から言えば、これはめずらしい。
たいてい、その日と次の日くらいでコメントは止まる。
そして、あとから読んでくださった方が例外的にコメントをくださる。
一般的には、だいたい、そのようなかたちだ。
ところが、この記事は、そうではなかった。
5日たっても、まだコンスタントにTBやコメントが届けられるのだ。
それだけ、多くの人が持続的に関心を持っている問題なのだろう。
そしておそらく、しばらくの時間をおかないと語りにくかった問題でもあるのだろう。
試みに、記事別のアクセス数を見てみたら251。
100アクセスあれば多い方だという各記事の中で、突出している。
これまで「沖縄・八重山探偵団」で、記事別アクセス一覧の欄外に消えるまでで最も多いアクセスのあった記事では1100を超えたが、これは例外中の例外。
250というアクセス数が、この「事件」への静かでありながら強い関心を示している。
じっさいに、、てぃーだ内の他のブログでも真摯な意見が交換されている。
ぼくの知る限り、あゆさんの「沖縄文学館」に集約されたリストが最も詳細。
よって、ここでは、そちらをご参照いただきたいと記して、責を塞いでおく。

前置きが長くなった。
ぼくは本心では、斎場御嶽にせよ、中グスクにせよ、久高島の拝所にせよ、長い長い祈りの場として伝えてきた人々の手に、一元的に在るべきだと思う。
逆に言えば、いくら世界遺産というシルシつきの観光名所となったところで、それは不特定多数の人の「持ち物」ではないと考える。
あえて強い言い方をすれば、たとえば中グスクが立ち入り禁止になることで聖地としての機能を保持できるのであれば、そうすべきであると思うのだ。
話が拡散するので、先ずは今回自分の目で見、話を聞いてきた中グスクに絞りたい。
中グスクの聖木伐採には、いくつかの要素が絡み合っている。
そもそも4000㎡にも及ぶ中グスクエリアの、どの木が聖木で、どれがそうでないかという問題はおいて、たしかに、世界遺産指定以後に多くの木々が伐採されてきた。
地権者による伐採があったという。管理母体による伐採があった。そして、それらには(納得できるかできないかは別として)それぞれの理由があった。
いま、その詳細を述べることは控えておくが、「聖なる場所を破壊しよう」と考えて樹木の伐採をおこなった者は皆無だということだけをここでは述べておきたい。
他者の心の中に踏み込んでいけない部分があるように、この世界には踏み込んではならない領分というものがある。
その、本来踏み込んではならない領分に、不特定多数の人間が踏み込まざるをえない状況を作り出したことこそが、問題の核心であると考える。
つまり、世界遺産指定というかたちで、より多くの人間を受け入れるシステムの中に中グスクをはじめとする聖域(すくなくとも聖域を含んだエリア)を組み込んだ時点で、それは行政的管理の権限の中に組み込まれることを認めたということなのだ。
管理責任者の論理からすれば、エリア内に危険因子を残しておくことは出来ない。
よって、ハブの住み着く可能性のある草叢や潅木は除去される。風で枝が落ちる可能性のある高木もまた除去される。そして、見学者に危険を及ぼす可能性のある石垣は補強されなけらばならない。
そのような大状況の中で、「聖域であること」を条件に、危険因子を保持することは、すでに不可能なのだ。
たとえば、識名園では(ここも、今回赴いて確認してきたのだが)、園内にあった拝所は、開園整備の一環として園外へと移動させられている。
具体的には3つの(日本式に言えば)祠が、入口横の事務棟の背後へと移転されているのだ。
事務所で聞いた答えは、園内にあると拝みに来た人が入園料を払わないといけなくなるので、入園料のいらない場所に移転したのだということであった。
いきなり降り始めた土砂降りの中で聞いたその話には、愕然とした。
もちろん、古式に則ったかたちで移転はおこなわれたに違いない。
しかし、それが「管理する側の論理」なのだ。
考えるに、終戦後半世紀あまり、ほとんど廃墟であった識名園だから、
つまり、拝所としての機能をほとんど失っていた期間の長い場所だから、
このようなふるまいが可能となったのに違いあるまい。
しかし考えてみれば、斎場御嶽だとて、期間の長短はあれ、拝所としての機能をほぼ停止していた時期が無いわけではない。そのことは意識しておく必要があるように思う。
つまり、永劫の聖地という考え方は、万世一系という神話と同様、時に思考を硬化させる可能性があるということだ。
今回はじめて訪れて確認した、中グスクに匹敵するほどのグスク機能を備えた大里グスクが現在ほぼグスクとしての形態を失っている(復元の15年計画は始まっている)のに、拝所としての機能を保持していることに鑑みれば、中グスクもまた、同様に廃墟としての姿の中で拝所のみの時代があったことは明らかである。
しかし、である。そのような拝所としての機能・論理を現実的に超えたところで、世界遺産・観光資源という論理が組織されてしまった以上、聖地としての意味は下位価値としてその下に組み込まれざるをえない。
だからあきらめようと言っているのではない。「世界遺産」を錦の御旗のように振り回すことの是非を、再確認する場を持ちたいと思っている。
もちろん、ユネスコの果たしてきた役割を軽視しようというつもりはない。
しかし、1992年にユネスコ世界遺産センターができてから、わずか14年という歳月で、この構想に万全の信頼と期待を抱くべきではないとも思っている。
文化遺産と自然遺産、そして複合遺産をあわせて現在世界で800あまりが登録されている世界遺産。
しかし、文化・自然の保存という目的が逆に今回のように文化・自然の破壊につながることは、おそらく例外ではない。
現在、内地に10(本州に9、近畿地方に4)ある世界遺産指定の地域・文化財が、逆に指定を受けることでもたらした問題(多くは観光地化の強化による環境破壊)は、まだ真摯に総括されていない。
その意味で、現在はまだ世界遺産指定の是非を問う実験期間であると思うのだ。
であれば、その実験は審問されなければならない。より望ましい現実のために。
果たして、斎場御嶽が世界遺産登録を受けなければ、今回の盗難事件(それは3月9日から10日にかけてのことであったとされる)が発生しなかったかといえば、それは分からない。
すでに香炉の盗難はくり返しおこなわれてきたという情報もある。
また、同様に世界遺産指定を受けなければ中グスクの聖木伐採がなかったかといえば、どうであろう(種々の情報からは、中グスクにかんしては世界遺産指定が聖木伐採の主要因であったと考えられるのではあるが)
だから、世界遺産指定も、問題系のひとつの要因に過ぎないといえば過ぎないのだが、しかし連綿と続く「事件」の背景(本質)に、やはり世界遺産指定は大きく関与しているはずなのだ。

娘と一緒に、近くの公園を散歩してきた。
整備されたばかりの公園に、二つ並んで置かれたベンチが目に付いた。
このベンチが、人生におけるかけがえのない場所となる人が、きっといる。
その人にとってみれば、この「場」を落書きや破壊で汚されることは耐え難いことだろう。
しかしその一方で、この公園には管理母体(市)があり、ベンチは「その人」の持ち物ではない。
もちろんここは、聖地・拝所といった、歴史という「多くの人の思い」が折り重なった場所ではない。
しかし積分すれば、聖地とて、その場所を「かけがえのない」と思う人、思われた時間の集積によって聖地たりえている。
逆に微分すれば、どこであれ、その場所を「かけがえのない」と思う人思う意識があれば、そこは侵すべからざる場所であるに違いない。
わかりやすいのは、自分の家であり、自分の部屋である。
家や部屋で考えれば、何が侵害なのかという認識は大多数が共有している。
斎場御嶽の事件の場合、こがね壺や香炉を盗まれることによって誰が何を侵されているのかが見えない(見えにくい)状況の中に現代という社会が置かれている構造が露呈している。
だから、この事件を論じる多くの人(ぼくも含めて)が、問題は盗難事件そのものにあるのではなく、そのような事件を誘発するこの社会構造にあるのだと観じている。
しかし、とも思うのだ。
「ここ」は、ある人にとってかけがえのない場所に、別の人が土足で踏み込むことを奨励する社会。
つまりは、観光地であるとか世界遺産であるとかといったコンセプトのもとに、本来聖地である(そこを聖地であると認識する者しか踏み込めない)場所を不特定多数の人間に対してオープンにして行く(それどころか、有効な対策もなく次々に呼び込む)こと自体が、やはり大きな問題ではないだろうか。
世界遺産指定をはずすという選択肢。いささかの退嬰をこめて言うならば、それこそが斎場御嶽を、そして中グスクを救う、最大にして最短の近道と思うのだ。
それができないというのであれば、KUWAさんが逆説的に言われる、「柵と鎖でがんじがらめにした聖域」も仕方がないと感じている。
いまは、観光至上(つまるところ経済至上)のシステムの中に組み込まれた聖域の何を守ることが優先順位かを考えるべき時である。それが対症療法に過ぎないのであれ何であれ。
そもそも「心の中の善を喚起する」場であるはずの聖域に対する犯罪が続発するのである以上。
ただし、かんじがらめにすべき対象が、じつに多種多様であり、ある意味で聖域を守る役割の人の手を鎖で縛らなければ聖域が破壊されるという大いなる皮肉こそが、この問題の一筋縄では行かない大きな要素となっているのであるけれども。

聖地・聖域を考えることは、難しい。
そもそもその場所が「聖」なる要件を、共有することが必ずしも容易ではないからだ。
ある者にとってみれば侵すべからざる場所が、別の者にとってみれば易々と踏みにじりうる場所であるということは、この社会にはいくらでもある。
たとえばAにとって花園ラグビー場は、人生のすべてを賭けうる神聖な殿堂であるが、B(ぼくでもいい)にとってみれば子どもを遊ばす広場でしかない。
そのとき、なぜその場がAにとって神聖な場所であるかを伝達することがまず必要だ(ただし、Aの価値観の中では)
次に、その場所を侵すべからざる場所であるという価値観を共有させることが必要だ。
しかし、ぼくはべつに花園ラグビー場広場に入っても緊張もしないし、ありがたいとも思わない。
あえて言えば、ストーンサークル風のモニュメントに沈む夕日を見るのが好きというだけだ。
ただ、その場を「かけがえのない」と思う多くの人たちがいるということを、さざざまなメディアによって理解している。
だから(という「以前に、社会の一員として)ラグビー場に落書きをしないし、備品を盗もうとも思わない。
そこで、あえて強い言い方をすれば、花園ラグビー場と斎場御嶽の「聖度」に、どれだけの差異があるのか、ということになる。
その差異を、だれに向かって、どのように理解させるか、理解させうるかという話になるのではないか。
「理解させる」という言い方が高圧的であることは承知しつつ。
斎場御嶽の盗難事件に心を痛めるほどの人は、「自分の心の問題」として自らに厳しく自問する。
そしてその結果、(傾向性として言っているいのだが)精神を純化させつつ内向してゆく。
そのような純化された精神が、この世界に存在すること自体は、とても尊いことだ。
ただし、そのように内向化する尊い自問のかたわらで、実際に聖地は破壊され続けている。
ぼく自身「何が出来るか」という自問自答の中にいて、
しかし、やはり「何かをしたい」と考えている。
現在、このブログを訪れてくださる方は、日に300人ほど。
しかし、その300人が一同に会する場面を一旦想像してみれば、
それが、どれほどものすごい人数であるかが実感できる。
そこでぼくは先ず、その人たちに語りかけてみることにしよう。
あなたは、世界遺産登録後にくり返される、聖地の破壊について
どのような意見や感想をお持ちですか?
じつにまとまらぬ文章となったが、
引き続き考えたいと思っている。
ご意見をいただければ幸いである。
Posted by び ん at 19:03│Comments(15)
この記事へのコメント
こんばんは はじめまして。
私は大浦湾が世界遺産になれば基地建設から守れるかと思っていましたが…
世界遺産になることによる問題もあるのですね。
沖縄を損なうものは基地だけではないし…
首里城の龍譚池にも外来種の魚が増えていると聞きました。
うちとこにブックマークさせていただきました。
これからもよろしくお願いします。
私は大浦湾が世界遺産になれば基地建設から守れるかと思っていましたが…
世界遺産になることによる問題もあるのですね。
沖縄を損なうものは基地だけではないし…
首里城の龍譚池にも外来種の魚が増えていると聞きました。
うちとこにブックマークさせていただきました。
これからもよろしくお願いします。
Posted by 亜衣 at 2006年03月22日 00:22
亜衣ちゃんだ(*^^*)
びんさんのように しっかりとした考えと意見を
文字に出来る方のところで 共感したり 亜衣ちゃんの意見を
聞いて頂いたりして 少しづつでも
亜衣ちゃんの わじわじ~が ゆるくなったり
強い決意みたいなモノや 納得するもの・・・
改めて考えること・・・イロイロ・・・が得られたら
良いなと思います。
いかんせん・・・えみんちゅ 頭の中身が チョット少なくて・・・(^▽^;)
びんさんのように しっかりとした考えと意見を
文字に出来る方のところで 共感したり 亜衣ちゃんの意見を
聞いて頂いたりして 少しづつでも
亜衣ちゃんの わじわじ~が ゆるくなったり
強い決意みたいなモノや 納得するもの・・・
改めて考えること・・・イロイロ・・・が得られたら
良いなと思います。
いかんせん・・・えみんちゅ 頭の中身が チョット少なくて・・・(^▽^;)
Posted by えみんちゅ at 2006年03月22日 00:52
こんばんは。いらっしゃいませ。
大浦湾。・・・どうでしょうか。そもそも国連そのものに対して敬意を払わない国の基地建設ですから・・・でも、きっと世界遺産に登録されなくても、大丈夫だと思いたいです。
たとえばぼくらみんな外来種ですし、過度に外来種に神経質になる必要はないかもしれないのですが、テラピア(でしたっけ?)は目に余りますね。不自然に生態系を壊す場合は、やはり何らかの対策が必要か、と。
いえ、こちらこそよろしくお願いします。
大浦湾。・・・どうでしょうか。そもそも国連そのものに対して敬意を払わない国の基地建設ですから・・・でも、きっと世界遺産に登録されなくても、大丈夫だと思いたいです。
たとえばぼくらみんな外来種ですし、過度に外来種に神経質になる必要はないかもしれないのですが、テラピア(でしたっけ?)は目に余りますね。不自然に生態系を壊す場合は、やはり何らかの対策が必要か、と。
いえ、こちらこそよろしくお願いします。
Posted by びん at 2006年03月22日 00:54
あ。インターセプト(笑)
↑が>亜衣さん
ここから↓
>えみんちゅさん
いえいえ、うまくまとめて書けなくて困っています。
のののさんみたいに、ちゃんと下書き書いてから記事にすればいいんですけどね。
わじわじ~は、大切なのではないかと思っています。
いろんなことに対するわじわじ~がなくなってしまったら
その時から、流されてしまうこともきっと増えるでしょうから。
でも、いつもわじわじ~してると健康にも美容にもよくないですから(笑)
きのうみたいなお祭りは、楽しめればいいな、なんて(^-^ゞ
いかんせん、かっぱえびせん(なんだ?笑)
↑が>亜衣さん
ここから↓
>えみんちゅさん
いえいえ、うまくまとめて書けなくて困っています。
のののさんみたいに、ちゃんと下書き書いてから記事にすればいいんですけどね。
わじわじ~は、大切なのではないかと思っています。
いろんなことに対するわじわじ~がなくなってしまったら
その時から、流されてしまうこともきっと増えるでしょうから。
でも、いつもわじわじ~してると健康にも美容にもよくないですから(笑)
きのうみたいなお祭りは、楽しめればいいな、なんて(^-^ゞ
いかんせん、かっぱえびせん(なんだ?笑)
Posted by びん at 2006年03月22日 01:02
びんさん 早速お返事ありがとうございました。
私は30代になって沖縄の現実を知るまで、政治とか国のやり方とか、
全然関心も知識もない人間でした。
だから、まだまだ考え方が甘いというか、単純というか…
「世界遺産登録=いいことばかり」としか思っていなかったので、
今回は成る程なあと考えさせていただく機会になりました。
「わじわじは大事」この言葉も胸に刻まれました。
えみんちゅさん ありがとね^^
私は30代になって沖縄の現実を知るまで、政治とか国のやり方とか、
全然関心も知識もない人間でした。
だから、まだまだ考え方が甘いというか、単純というか…
「世界遺産登録=いいことばかり」としか思っていなかったので、
今回は成る程なあと考えさせていただく機会になりました。
「わじわじは大事」この言葉も胸に刻まれました。
えみんちゅさん ありがとね^^
Posted by 亜衣 at 2006年03月22日 01:15
南西フランスは、いかがでした?(^-^>
よく言われることですが、何歳で何を始めたということは、まったく本質的なことではないと思います。問題は、やはり「いま何をしているか」、そして「これから何をするのか」ではないでしょうか。
だなんて、わかったようなことをつい言ってしまいました。すみません。
書かれたもの、ほんの少しですが読ませていただいて、問題意識の持たれ方に教わるべき部分が多々あると思いました。僭越な言い方ですが。
そういう風に言っていただけたこと、たいへんうれしく思っています。
えみんちゅさん、ありがとね^^;
よく言われることですが、何歳で何を始めたということは、まったく本質的なことではないと思います。問題は、やはり「いま何をしているか」、そして「これから何をするのか」ではないでしょうか。
だなんて、わかったようなことをつい言ってしまいました。すみません。
書かれたもの、ほんの少しですが読ませていただいて、問題意識の持たれ方に教わるべき部分が多々あると思いました。僭越な言い方ですが。
そういう風に言っていただけたこと、たいへんうれしく思っています。
えみんちゅさん、ありがとね^^;
Posted by びん at 2006年03月22日 01:35
こんな記事を見つけました。びんさんのお考えと、だいたい重なるでしょうか。
http://www.gakugei-pub.jp/judi/forum/forum13/f13006.htm
「一元的に在る」ことについては、無理があるのではと私は思います。びんさんも「本心では」と断られていますが。尚氏遺産の国宝指定に関するとらひこさんの見解(目ウロコ)を読んで、改めてそう思いました。物と場所では、問題が違うかもしれませんが・・・。
http://www.gakugei-pub.jp/judi/forum/forum13/f13006.htm
「一元的に在る」ことについては、無理があるのではと私は思います。びんさんも「本心では」と断られていますが。尚氏遺産の国宝指定に関するとらひこさんの見解(目ウロコ)を読んで、改めてそう思いました。物と場所では、問題が違うかもしれませんが・・・。
Posted by あゆ at 2006年03月22日 12:50
あ、別に「読め」というわけではありません(汗) 問題の一例を見つけただけでした。
Posted by あゆ at 2006年03月22日 12:59
そうですね。鳴海さんのご意見に重なる部分が大きいと思います。景観保存・文化財保護とまちおこしの関係に、やはり複雑なネジレの生じがちなことは認識しつつ。
瑣末なことですが中上健次の誤植は気になりました。また、もっと瑣末なことですが天神崎トラストの「やりっぱなし」に対する(ちょっとだけ土地所有しているのです)いささかの疑問を思い出しつつ。もちろん日本のトラスト運動に先鞭を着けた役割は、これもまた十分に評価しつつ。
尚家遺産の国宝指定、たいへんよろこばしいことです!
直截的には、戦前指定の12件23点のうち18点(「特別展・甦る沖縄」による)の備考に「戦災滅失」の並ぶ切なさが、いささかでも緩和されるという意味で・・・
「この問題」に関しては、どうしてもぼく自身がネジレますね。常に「踏み込むべからざる領域に踏み込んでいる」という意識を飼いならしつつの訪問になりますので。
もう少しスナオに論じてみようと思っています。
引用すべき文言は、やはり引用しつつ。・・・妄言多謝。
付記。「目ウロコ」は、ちょっとコワイ(笑)
瑣末なことですが中上健次の誤植は気になりました。また、もっと瑣末なことですが天神崎トラストの「やりっぱなし」に対する(ちょっとだけ土地所有しているのです)いささかの疑問を思い出しつつ。もちろん日本のトラスト運動に先鞭を着けた役割は、これもまた十分に評価しつつ。
尚家遺産の国宝指定、たいへんよろこばしいことです!
直截的には、戦前指定の12件23点のうち18点(「特別展・甦る沖縄」による)の備考に「戦災滅失」の並ぶ切なさが、いささかでも緩和されるという意味で・・・
「この問題」に関しては、どうしてもぼく自身がネジレますね。常に「踏み込むべからざる領域に踏み込んでいる」という意識を飼いならしつつの訪問になりますので。
もう少しスナオに論じてみようと思っています。
引用すべき文言は、やはり引用しつつ。・・・妄言多謝。
付記。「目ウロコ」は、ちょっとコワイ(笑)
Posted by びん at 2006年03月22日 14:32
やっぱり^ ^;
ところで、
>つまりは、観光地であるとか世界遺産であるとかといったコンセプトのもとに、本来聖地である(そこを聖地であると認識する者しか踏み込めない)場所を不特定多数の人間に対してオープンにして行く(それどころか、有効な対策もなく次々に呼び込む)こと自体が、やはり大きな問題ではないだろうか
このように言ってしまうと、斎場御嶽のことで直接の責任を負う旧知念村、現南城市には、とても気の毒ではないかと思ってしまいました。管理側としては、観光客をも含めて、人の良心を信じたゆえの管理の仕方だったと思うからです。
もちろん、この言葉が南城市へのものではなく、そういったことを可能にする社会構造に対するものであることは、記事を読めばわかるのですが。
ところで、
>つまりは、観光地であるとか世界遺産であるとかといったコンセプトのもとに、本来聖地である(そこを聖地であると認識する者しか踏み込めない)場所を不特定多数の人間に対してオープンにして行く(それどころか、有効な対策もなく次々に呼び込む)こと自体が、やはり大きな問題ではないだろうか
このように言ってしまうと、斎場御嶽のことで直接の責任を負う旧知念村、現南城市には、とても気の毒ではないかと思ってしまいました。管理側としては、観光客をも含めて、人の良心を信じたゆえの管理の仕方だったと思うからです。
もちろん、この言葉が南城市へのものではなく、そういったことを可能にする社会構造に対するものであることは、記事を読めばわかるのですが。
Posted by あゆ at 2006年03月22日 15:39
南城市の管理担当部局に対する批判の意識はありませんでした。
今回、南城市の担当者の対応は、他に比べてもじつに誠意あるものでした。そのことを別にしても。
ただ、(問題の核心がずれるかもしれませんが)ぼくには、たとえば男子禁制であったはずの斎場御嶽に、なぜ男性の立ち入りが可能になったかという点に対して、納得できる説明を聞いた(読んだ)覚えがありません。
もちろんジェンダーの位相だけではなく、ぼくは、ぼくらの身体がそうであるように、「この世界」には幾重もの「聖ー俗」の差異(それが壁であるかカーテンであるかは問わず)が存在することを認め合う社会のほうが、より健全であるように思えるのです。
そのような視点に立てば、ではなにが「俗」なのかということになるでしょうが、最低限、「盗み」は「俗」の最たるものですよね。
「未必の悪意」を摘み取るために、時にさりげなく柵(それは空間的距離である場合も、心理的距離である場合もあるでしょう)を置くことこそが、あるいは「教育」なのかもしれないと思っています。
「良心」の問題。・・・
また、貴重な課題をいただきました。
今回、南城市の担当者の対応は、他に比べてもじつに誠意あるものでした。そのことを別にしても。
ただ、(問題の核心がずれるかもしれませんが)ぼくには、たとえば男子禁制であったはずの斎場御嶽に、なぜ男性の立ち入りが可能になったかという点に対して、納得できる説明を聞いた(読んだ)覚えがありません。
もちろんジェンダーの位相だけではなく、ぼくは、ぼくらの身体がそうであるように、「この世界」には幾重もの「聖ー俗」の差異(それが壁であるかカーテンであるかは問わず)が存在することを認め合う社会のほうが、より健全であるように思えるのです。
そのような視点に立てば、ではなにが「俗」なのかということになるでしょうが、最低限、「盗み」は「俗」の最たるものですよね。
「未必の悪意」を摘み取るために、時にさりげなく柵(それは空間的距離である場合も、心理的距離である場合もあるでしょう)を置くことこそが、あるいは「教育」なのかもしれないと思っています。
「良心」の問題。・・・
また、貴重な課題をいただきました。
Posted by びん at 2006年03月22日 16:38
知る事により、守られるもの、壊れるもの、物質的
精神的、合致するのは困難かもしれません。スーツ姿
のマサイ族も、外側の人間にしてみれば、唖然として
自己の観念とのギャップに・・え?って脱力感もあった
ものです。(撮影の為に、らしく、する)でも、その「らし
さ」を造ってる(私も含めて)者が存在してる。比較の
対象事ではないかもしれませんが、人はもう、曝け出さ
れたものへ対して想い、願い、祈りは、あゆさんが書か
れているように、良心を信じる、だと思います。信じてる
んだと思います。
今という現実は昨夜の未来であり、明日の過去となる。
時は今、今の積み重ねながら、結局、円、まるになる
tみたいね?だから、形を変化させながら進化させていく
のも文明。でも、何時の世にも・・太古より「そこ」に存在
した精神御神。それが崩壊したら・・・悲しい。山が泣け
ば海も泣き、空の涙は地の涙。生命の繋がり。ジュゴン
子々孫々の安穏な未来、どれも別々ではないと思いま
す。山原の森の生態系にも影響が出る海上基地。
私、何を書いてるんだか、すみません。思考が分散して
自分で訳分からなくなってしまいました。尊いものって
何なのかしら?って、ふと、です。やはり、現場の論議
が大切だと思います。もっと話し合うべきだと思います。
方向性ではもっと守れるものが有ると思いますし。長々
とすみません。そして、愛、です。(笑)
精神的、合致するのは困難かもしれません。スーツ姿
のマサイ族も、外側の人間にしてみれば、唖然として
自己の観念とのギャップに・・え?って脱力感もあった
ものです。(撮影の為に、らしく、する)でも、その「らし
さ」を造ってる(私も含めて)者が存在してる。比較の
対象事ではないかもしれませんが、人はもう、曝け出さ
れたものへ対して想い、願い、祈りは、あゆさんが書か
れているように、良心を信じる、だと思います。信じてる
んだと思います。
今という現実は昨夜の未来であり、明日の過去となる。
時は今、今の積み重ねながら、結局、円、まるになる
tみたいね?だから、形を変化させながら進化させていく
のも文明。でも、何時の世にも・・太古より「そこ」に存在
した精神御神。それが崩壊したら・・・悲しい。山が泣け
ば海も泣き、空の涙は地の涙。生命の繋がり。ジュゴン
子々孫々の安穏な未来、どれも別々ではないと思いま
す。山原の森の生態系にも影響が出る海上基地。
私、何を書いてるんだか、すみません。思考が分散して
自分で訳分からなくなってしまいました。尊いものって
何なのかしら?って、ふと、です。やはり、現場の論議
が大切だと思います。もっと話し合うべきだと思います。
方向性ではもっと守れるものが有ると思いますし。長々
とすみません。そして、愛、です。(笑)
Posted by ルビーの涙 at 2006年03月22日 17:59
ちょっと面白い事を書いている方を発見したので、
話がずれて申し訳ございませんが、ご一読下さい。
(「う」さんの日記より抜粋)
「三年ほど前に、ちょっとおもしろい話題がテレビに流れていました。
とある河川敷でゴミの不法投棄が止まらなくなってしまったとの事。
立て札や柵などで対処し、予算を投じて撤去してもしばらくすると元のゴミの山に戻ってしまう。
苦慮した挙句、管轄省庁がたてた作戦はほとんどヤケクソと言えるもので、1メートル四方ぐらいのミニチュア(赤く塗った板を重ねただけ)の鳥居を組み立てて数カ所に置いてみるというものだった。
するとそれまでどんな脅し文句の看板でも止められなかった不法投棄がとたんに少なくなったと云うのです。
ゴミという自分から出るケガレと、川や海という清浄の象徴が、
あの鳥居の単純なかたちを見る事で即座に認識され、
「バチあたるゾ」というインスピレーションにつながったのではないかと思われます。
日本人の深層にある「清浄とけがれ」の観念が、笑えるかたちで
ニュースとなっていたような気がしました。」
北海道でのことだそうです。
聖地と知りながら荒らされる場所があり、聖地だぞと表示されたら
荒らされなくなる場所あり、いろいろですね。
余談カキコすみませんでした。
話がずれて申し訳ございませんが、ご一読下さい。
(「う」さんの日記より抜粋)
「三年ほど前に、ちょっとおもしろい話題がテレビに流れていました。
とある河川敷でゴミの不法投棄が止まらなくなってしまったとの事。
立て札や柵などで対処し、予算を投じて撤去してもしばらくすると元のゴミの山に戻ってしまう。
苦慮した挙句、管轄省庁がたてた作戦はほとんどヤケクソと言えるもので、1メートル四方ぐらいのミニチュア(赤く塗った板を重ねただけ)の鳥居を組み立てて数カ所に置いてみるというものだった。
するとそれまでどんな脅し文句の看板でも止められなかった不法投棄がとたんに少なくなったと云うのです。
ゴミという自分から出るケガレと、川や海という清浄の象徴が、
あの鳥居の単純なかたちを見る事で即座に認識され、
「バチあたるゾ」というインスピレーションにつながったのではないかと思われます。
日本人の深層にある「清浄とけがれ」の観念が、笑えるかたちで
ニュースとなっていたような気がしました。」
北海道でのことだそうです。
聖地と知りながら荒らされる場所があり、聖地だぞと表示されたら
荒らされなくなる場所あり、いろいろですね。
余談カキコすみませんでした。
Posted by ポータラカ at 2006年03月22日 22:46
あらゆるものごとが「つながって」いるという偶然=必然の中、「私」という意識(自我と言っても、アイデンティティと呼んでもいいのでしょうけれど)を超えた「私」に、くり返しくり返し気づかせられます。沖縄では、その頻度・濃度がじつに高く、その不思議さに惹きつけられたまま舞い戻るということをくり返してきました。
そうですね。ただ感じるままの状態、つまり、「知る」を知らない状態に戻ったほうがいいという乱暴な論を述べたのかもしれません。
ただしかし、「祈り」にシステムは要らないかもしれませんが、所作は必要だと思っています。これも沖縄から教わったこと。神が「ある」から祈るのか、祈りによって神が生まれるのか、いずれも「是」ではないのでしょうか。・・・だから?
だから、言いたいことは「神を殺すな」であろうと自分では思っています。
そしてそれはやはり、「人を殺すな」「自然を殺すな」「命を殺すな」ということなのでしょうね。
そうですね。ただ感じるままの状態、つまり、「知る」を知らない状態に戻ったほうがいいという乱暴な論を述べたのかもしれません。
ただしかし、「祈り」にシステムは要らないかもしれませんが、所作は必要だと思っています。これも沖縄から教わったこと。神が「ある」から祈るのか、祈りによって神が生まれるのか、いずれも「是」ではないのでしょうか。・・・だから?
だから、言いたいことは「神を殺すな」であろうと自分では思っています。
そしてそれはやはり、「人を殺すな」「自然を殺すな」「命を殺すな」ということなのでしょうね。
Posted by びん at 2006年03月22日 22:48
ありゃ。またインターセプト(苦笑)
↑が>ルビーの涙さん
↓が>ポータラカさん です(コメレスに名前書かないぼくが悪いのです・汗)
その話、詳細は忘れましたが記憶していました。
最近はあまり見かけなくなりましたが、「立ち○○禁止」の鳥居の絵のバリエーションですよね。
それは、3年後の今も「機能」しているのでしょうか?
きわめて個人的な感想として、その発想自体が「バチあたり」なのかもしれないな、なんて思ったことを思い出しました。
そのことを思いついた方は、ほんとうに切実であったのだろうと今は思うのですが。
↑が>ルビーの涙さん
↓が>ポータラカさん です(コメレスに名前書かないぼくが悪いのです・汗)
その話、詳細は忘れましたが記憶していました。
最近はあまり見かけなくなりましたが、「立ち○○禁止」の鳥居の絵のバリエーションですよね。
それは、3年後の今も「機能」しているのでしょうか?
きわめて個人的な感想として、その発想自体が「バチあたり」なのかもしれないな、なんて思ったことを思い出しました。
そのことを思いついた方は、ほんとうに切実であったのだろうと今は思うのですが。
Posted by びん at 2006年03月22日 22:56
お返事が遅くなる場合があります。あしからず。