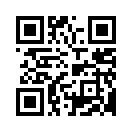2007年08月23日
ひとつ崩れて秋の風
(前の記事から続きます)
「入道雲ひとつ崩れて秋の風」だなんて
入道雲(夏)と秋の風(もちろん秋)の季語の入り乱れた
むちゃくちゃな句を書いてしまって、恥ずかしくなりました。
いちおう、夏から秋への移り変わりをあらわそうだなんて、
自分ではイイワケを考えていたのではありますが・・・
で、結局これは、芭蕉句のパクリ、
というのが言いすぎなら影響下にある駄句ですな(汗)
芭蕉が「入道雲」という言葉を使ったとは聞きませんが、
彼には、「秋の風」で終わる句が多い。
おそらく、一番よく知られているのが、
物言えば唇寒し秋の風
でありましょう。
「これって、諺(ことわざ)じゃないの?」と思っている人も多いはず。
つまり、それだけ人口に膾炙(かいしゃ)している(よく知られている)ってことですよね。
あるいは、
塚も動け我泣声(わがなくこえ)は秋の風
奥の細道の旅で、知人の墓に詣でたときの作です。
同じときに、このような句も吟じていますね。
あかあかと日は難面(つれなく)も秋の風
夕日のむなしさ、せつなさと、秋の風とを重ねている。
そのように吟ずることで、亡き人と自分をなぐさめている。
「奥の細道」より前、「野ざらし紀行」の旅の句には、こんなものがありました。
旅寝して我が句を知れや秋の風
芭蕉にとって、どうも秋風は旅のつれづれをなぐさめる友達だったようです。
また、「笈(おい)の小文(こぶみ)」の旅では、
旅に飽きてけふ幾日やら秋の風
なんて句を吟じています。
旅の詩人・松尾芭蕉も、旅にあきることもあったんですね。
古来、「秋の風」と「飽きる」は掛詞の定番。
ま、「ふとんがふっとんだ」とか、「電話に出んわ」とかいった感じです。
もちろん芭蕉もそのことをよく知っていて、句そのものに「飽き」を表現したのでしょう。
もうひとつ、「笈の小文」から。
見送りのうしろや寂し秋の風
名古屋に滞在していたとき、名古屋の門人(弟子)の野水(やすい)が上方(京・大阪)に出発し、
それを見送ったときの句。
人を見送ったあと、背中がさびしく感じるというのは、ぼくらにもわかる感覚ですよね。
身にしみて大根からし秋の風
だなんて句もあります。
信州(長野県)更科へ旅する「更科紀行」の句ですね。
「身にしみる」と、「タイコンの辛さがしみる」のミックス^^
この紀行文の最初には、
「更科の里、姥捨山の月見んこと、しきりにすすむる秋風の心に吹きさわぎて」
なんて書いてあります。
つまり松尾芭蕉という人は、秋風が吹くと旅をしたくてたまらなくなる人だったようで。
・・・よくわかります。
もうひとつ、「奥の細道」から。
桃の木のその葉散らすな秋の風
加賀(石川県)の山中温泉での句です。
秋風好きな芭蕉も、秋風が木の葉を散らすのはイヤだったようですね。
と言いつつ、芭蕉(バナナではなく、実のならない芭蕉)の大きな葉が、
風に吹き破られるのが大好きで「芭蕉」なんて名を名乗っているのですから、
あるいは「その葉散らすな」も反語だったかもしれません。
「いやよいやよも・・・」というアレですね(苦笑)
やはり奥の細道の旅、山中温泉での句。
石山の石より白し秋の風
「秋」といえば「白」。風水(陰陽五行)では、そうなっています。
これにもとづいて名乗ったのが北原白秋ですよね。
芭蕉は、その土地土地に「挨拶」するのが好きでしたから、
山中温泉では、こんな句もつくっています。
山中や菊はたおらぬ湯の匂
たちのぼる湯の香がいくらつよくても菊の花は折らないだろう、
だなんて、いいですねぇ。
蜘蛛何と音(ね)をなにと鳴く秋の風
なんて句もあります。
クモが鳴くなんて聞いたことありませんが、
これは、『枕草子』「虫は」の段に出てくる、鳴く蓑虫を意識しているといわれています。
ミノムシの親は、子どもに蓑を着せ「秋風が吹く頃に帰ってくるよ」行ったまま帰ってこない。
置き去りにされたミノムシの子どもは、「ちちよ、ちちよ」と、はかなげに鳴く、というのですね。
清少納言のミノムシを、芭蕉がクモに変えた意図は、よくわかりません。
ちょうど目の前にクモがいたのでしょうか?あるいは、クモという発音がよかった?
【補注】「クモが鳴くなんて聞いたことがない」と書きましたが、
子どもの頃に捕ったジグモは、たしか袋から出すと、キュッキュという警戒音を出したように思います。
ところで、「鳴く 蜘蛛」「クモ 鳴く」などでググっていたら、こんなステキなスレを見つけてしまいました。
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/wild/1149152678/
もと生物部員の血がさわぎます(苦笑)
ムシのニガテな人は、アクセス禁止です^^;
結句(最終句)が「秋の風」で終わる句は、こんなふうにたくさんあるのですが(まだあるでしょう)
それ以外の場所に「秋の風」が出てくる芭蕉句は、なかなか見つかりません。
かろうじて、
秋の風伊勢の墓原(はかはら)なほ凄し
というのがありました。
「奥の細道」の旅を終えて、故郷の伊賀に帰る途中、
伊勢(三重県)で、荒木田神主の墓所に詣でたときの句です。
これは、芭蕉が敬愛してやまなかった歌人・西行の、
「吹きわたす風にあはれをひとしめていづくもすごき秋の夕暮」という歌を意識したもの。
「等し」という形容詞を「等しむ」と動詞に使って、「どこもかしこもあわれを感じる」というのですね。
古語の「凄し」「物凄し」には、「ものさびしい」あるいは「ぞっとする」という意味が多く含まれていました。
たとえば『源氏物語』賢木(さかき)巻の、
「かれがれなる虫の音に松風すごく吹きあはせて」
などという例があります。これは、「ものさびしい」ほうですね。
同じ『源氏物語』でも、
「あたりさえすごききに、板屋のかたはらに堂建てて行へる尼の住まひ」(夕顔)
になると、「ぞっと身にしみて寒気を感じる」「鬼気迫るようなおそろしさ」のほうです。
1000年たって、「ぞっとする」から、よい意味でも悪い意味でも使われるようになったのが「すごい」です。
(今年が『源氏物語』1000年と言われています。もちろん1年で全部書いたわけではありませんが、
1007年には、紫式部が確実に『源氏物語』を書いていたという確実な証拠がありますので。)
さてさて、いよいよ「物言えばくちびる寒き」になって来ました(苦笑)
で、「入道雲ひとつ崩れて」のほうなんですが、これは、
雲の峰幾つ崩て月の山
ですねぇ、どう考えても。
「奥の細道」のクライマックスのひとつ、
羽黒山に引き続いて、月山(がっさん)に登ったときの句です。
「ひとつ」というのは、
生きながら一つに氷る海鼠(なまこ)かな
鷹一つ見付けてうれし伊良湖崎(いらござき)
一家(ひとつや)に遊女もねたり萩と月
月影や四門四宗(しもんししゅう)もただ一つ
(善光寺が浄土宗・禅宗・真言宗・律宗の四宗をあわせた寺院なので)
などといくつか見られますが、「秋の風」ほど目立つ言葉ではないです。
こうやって見ていると、芭蕉という俳諧師(はいかいし。近代でいえば俳人)が、
いかに「秋の詩人」であったが、よくわかります。
最後に、おそらく誰もが知っている芭蕉の句を。
秋深し隣は何をする人ぞ
きのうの夜から降り始めた雨は、
朝方に止んで、いよいよ秋めいてきました。

夾竹桃夏の終わりの雨を受く びん
・・・またかよ(笑)
「入道雲ひとつ崩れて秋の風」だなんて
入道雲(夏)と秋の風(もちろん秋)の季語の入り乱れた
むちゃくちゃな句を書いてしまって、恥ずかしくなりました。
いちおう、夏から秋への移り変わりをあらわそうだなんて、
自分ではイイワケを考えていたのではありますが・・・
で、結局これは、芭蕉句のパクリ、
というのが言いすぎなら影響下にある駄句ですな(汗)
芭蕉が「入道雲」という言葉を使ったとは聞きませんが、
彼には、「秋の風」で終わる句が多い。
おそらく、一番よく知られているのが、
物言えば唇寒し秋の風
でありましょう。
「これって、諺(ことわざ)じゃないの?」と思っている人も多いはず。
つまり、それだけ人口に膾炙(かいしゃ)している(よく知られている)ってことですよね。
あるいは、
塚も動け我泣声(わがなくこえ)は秋の風
奥の細道の旅で、知人の墓に詣でたときの作です。
同じときに、このような句も吟じていますね。
あかあかと日は難面(つれなく)も秋の風
夕日のむなしさ、せつなさと、秋の風とを重ねている。
そのように吟ずることで、亡き人と自分をなぐさめている。
「奥の細道」より前、「野ざらし紀行」の旅の句には、こんなものがありました。
旅寝して我が句を知れや秋の風
芭蕉にとって、どうも秋風は旅のつれづれをなぐさめる友達だったようです。
また、「笈(おい)の小文(こぶみ)」の旅では、
旅に飽きてけふ幾日やら秋の風
なんて句を吟じています。
旅の詩人・松尾芭蕉も、旅にあきることもあったんですね。
古来、「秋の風」と「飽きる」は掛詞の定番。
ま、「ふとんがふっとんだ」とか、「電話に出んわ」とかいった感じです。
もちろん芭蕉もそのことをよく知っていて、句そのものに「飽き」を表現したのでしょう。
もうひとつ、「笈の小文」から。
見送りのうしろや寂し秋の風
名古屋に滞在していたとき、名古屋の門人(弟子)の野水(やすい)が上方(京・大阪)に出発し、
それを見送ったときの句。
人を見送ったあと、背中がさびしく感じるというのは、ぼくらにもわかる感覚ですよね。
身にしみて大根からし秋の風
だなんて句もあります。
信州(長野県)更科へ旅する「更科紀行」の句ですね。
「身にしみる」と、「タイコンの辛さがしみる」のミックス^^
この紀行文の最初には、
「更科の里、姥捨山の月見んこと、しきりにすすむる秋風の心に吹きさわぎて」
なんて書いてあります。
つまり松尾芭蕉という人は、秋風が吹くと旅をしたくてたまらなくなる人だったようで。
・・・よくわかります。
もうひとつ、「奥の細道」から。
桃の木のその葉散らすな秋の風
加賀(石川県)の山中温泉での句です。
秋風好きな芭蕉も、秋風が木の葉を散らすのはイヤだったようですね。
と言いつつ、芭蕉(バナナではなく、実のならない芭蕉)の大きな葉が、
風に吹き破られるのが大好きで「芭蕉」なんて名を名乗っているのですから、
あるいは「その葉散らすな」も反語だったかもしれません。
「いやよいやよも・・・」というアレですね(苦笑)
やはり奥の細道の旅、山中温泉での句。
石山の石より白し秋の風
「秋」といえば「白」。風水(陰陽五行)では、そうなっています。
これにもとづいて名乗ったのが北原白秋ですよね。
芭蕉は、その土地土地に「挨拶」するのが好きでしたから、
山中温泉では、こんな句もつくっています。
山中や菊はたおらぬ湯の匂
たちのぼる湯の香がいくらつよくても菊の花は折らないだろう、
だなんて、いいですねぇ。
蜘蛛何と音(ね)をなにと鳴く秋の風
なんて句もあります。
クモが鳴くなんて聞いたことありませんが、
これは、『枕草子』「虫は」の段に出てくる、鳴く蓑虫を意識しているといわれています。
ミノムシの親は、子どもに蓑を着せ「秋風が吹く頃に帰ってくるよ」行ったまま帰ってこない。
置き去りにされたミノムシの子どもは、「ちちよ、ちちよ」と、はかなげに鳴く、というのですね。
清少納言のミノムシを、芭蕉がクモに変えた意図は、よくわかりません。
ちょうど目の前にクモがいたのでしょうか?あるいは、クモという発音がよかった?
【補注】「クモが鳴くなんて聞いたことがない」と書きましたが、
子どもの頃に捕ったジグモは、たしか袋から出すと、キュッキュという警戒音を出したように思います。
ところで、「鳴く 蜘蛛」「クモ 鳴く」などでググっていたら、こんなステキなスレを見つけてしまいました。
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/wild/1149152678/
もと生物部員の血がさわぎます(苦笑)
ムシのニガテな人は、アクセス禁止です^^;
結句(最終句)が「秋の風」で終わる句は、こんなふうにたくさんあるのですが(まだあるでしょう)
それ以外の場所に「秋の風」が出てくる芭蕉句は、なかなか見つかりません。
かろうじて、
秋の風伊勢の墓原(はかはら)なほ凄し
というのがありました。
「奥の細道」の旅を終えて、故郷の伊賀に帰る途中、
伊勢(三重県)で、荒木田神主の墓所に詣でたときの句です。
これは、芭蕉が敬愛してやまなかった歌人・西行の、
「吹きわたす風にあはれをひとしめていづくもすごき秋の夕暮」という歌を意識したもの。
「等し」という形容詞を「等しむ」と動詞に使って、「どこもかしこもあわれを感じる」というのですね。
古語の「凄し」「物凄し」には、「ものさびしい」あるいは「ぞっとする」という意味が多く含まれていました。
たとえば『源氏物語』賢木(さかき)巻の、
「かれがれなる虫の音に松風すごく吹きあはせて」
などという例があります。これは、「ものさびしい」ほうですね。
同じ『源氏物語』でも、
「あたりさえすごききに、板屋のかたはらに堂建てて行へる尼の住まひ」(夕顔)
になると、「ぞっと身にしみて寒気を感じる」「鬼気迫るようなおそろしさ」のほうです。
1000年たって、「ぞっとする」から、よい意味でも悪い意味でも使われるようになったのが「すごい」です。
(今年が『源氏物語』1000年と言われています。もちろん1年で全部書いたわけではありませんが、
1007年には、紫式部が確実に『源氏物語』を書いていたという確実な証拠がありますので。)
さてさて、いよいよ「物言えばくちびる寒き」になって来ました(苦笑)
で、「入道雲ひとつ崩れて」のほうなんですが、これは、
雲の峰幾つ崩て月の山
ですねぇ、どう考えても。
「奥の細道」のクライマックスのひとつ、
羽黒山に引き続いて、月山(がっさん)に登ったときの句です。
「ひとつ」というのは、
生きながら一つに氷る海鼠(なまこ)かな
鷹一つ見付けてうれし伊良湖崎(いらござき)
一家(ひとつや)に遊女もねたり萩と月
月影や四門四宗(しもんししゅう)もただ一つ
(善光寺が浄土宗・禅宗・真言宗・律宗の四宗をあわせた寺院なので)
などといくつか見られますが、「秋の風」ほど目立つ言葉ではないです。
こうやって見ていると、芭蕉という俳諧師(はいかいし。近代でいえば俳人)が、
いかに「秋の詩人」であったが、よくわかります。
最後に、おそらく誰もが知っている芭蕉の句を。
秋深し隣は何をする人ぞ
きのうの夜から降り始めた雨は、
朝方に止んで、いよいよ秋めいてきました。
夾竹桃夏の終わりの雨を受く びん
・・・またかよ(笑)
Posted by び ん at 12:45│Comments(2)
│日々のこと
この記事へのコメント
久々に授業を受けている気分になりました~(笑)
古典は、いいですね~
古典は、いいですね~
Posted by とんとんみーかりかり at 2007年08月23日 13:31
はい、かりかりさん、授業態度「A」です。
あとは、レポートでがんばってください(笑)
あとは、レポートでがんばってください(笑)
Posted by び ん at 2007年08月23日 19:36
at 2007年08月23日 19:36
 at 2007年08月23日 19:36
at 2007年08月23日 19:36お返事が遅くなる場合があります。あしからず。