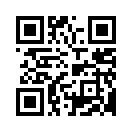2006年02月02日
さらに「サン」のこと
仲村清司さんの『沖縄学』が出た(新潮文庫、2001年2月1日刊)
4年前に双葉社から出た『沖縄人解体真書 ザ・ウチナーンチュ』の文庫版だ。
「ウチナーンチュ丸裸」というサブタイトルが、オクテな探偵団にはちょいと赤面ものなのだが(変?)
持ってきたのは・・・
うーむ。いま試験中だから記事リンクしないでおく。沖縄本ばかり読んでないで、しっかり勉強しなさいね。・・・オレもだな。

その中に、「サン」があった。
こんな説明。
旧暦8月は魔物が多い月といわれ、9~13日に桑の小枝とススキを束ねたサンを家の角や門などに差し、魔物の進入を防ぐ。また、その時期に限らず、サンは料理の上にのせたりもします。
『沖縄人解体真書』はもちろん愛読書のひとつだから、もう何度か読んだはずなのに。すっかり忘れ果てていた。
「家の角や門などに差」すのであれば、これはまったく内地の、ヒイラギに刺したイワシの頭と一緒だ。
(おまけに今が、ちょうどその節分!)
魔除けのヒイラギが、中世ヨーロッパでも同じはたらきをしたことは有名。
「サン(サングヮー)」も、『沖縄人解体真書』(『沖縄学』)の記述だと、むしろ旧暦8月の門飾りにその起源があり、食事などに乗せるのは、そこからの(つまり魔除け、厄除け)からの派生型であると読み取れる。
家に帰って「沖縄・八重山探偵団」を見ると、源氏パイさんのコメントがあった。
ずいぶん放置してしまったのは、月末締め切りの原稿で首が回らなかったから。スミマセン。ぐるぐる。
源氏パイ説では、「藁算」から来ているのではないかという。
形態の類似を鋭くとらえた、さすがに画家ならではの卓見だ。
藁算は、竹富島の喜宝院蒐集館が有名。インカ帝国の縄文字と結びつけられたりもする。
「算」と書いたのは、(詳しく書かずに言うのは気が引けるが)そのイメージがあったから。
ただ、数字や文字を記録するための技術と魔除けとが、どうしても結びつかなかった。
ぼくは竹富島に行ったことがないので(「しきた盆」と呼ばれるその姿は、石垣島から何度も眺めたのだが)、喜宝院蒐集館にも当然行ったことがない。
だから、イメージにあったのは、首里の県立博物館にある民具としてのワラ製玩具だった。
玩具であれば、魔除けとは直結する。
というより、むしろ多くの玩具は、魔除けが変化したものだというのは民俗学の通説だ。
すぐに思い浮かぶのは、やはり八重山のカジマヤー(風車)。
内地でいえば、獅子頭、それから鈴、トラの張り子・・・。
『沖縄学』を持ってきた、試験中の人は、「依り代(ヨリシロ)」だと言い張る。
つまり、漂う霊を閉じ込めるためのシンプルな装置。
これもかなり納得した(ふだんは、あまり納得しないのだが)。
そう言われて思い出したのは、東北地方のオシラサマ。
玩具であり、魔除けである。
地域によって、さまざまな形があるが、頭(カシラ)があるということだけは一致している。
ぼくには、サンの結び目が、頭に見えるのだ。(それは、あるいはジーファーの形態にもかかわっていると思っている)
そもそも「人形」が、もともとは「ヒトガタ」、つまりヨリシロであり魔除けであった。
だから、「依り代」という意見にも納得した。
そして何よりも、「結ぶ」ことによって霊を閉じ込めたり、あるいは強い力を生み出す、そのシンプルな「結ぶ力」への信頼が、サン(サングヮー)からは感じられる。
「縄文」というマジカル・ワードですべて納得した気にはなりたくないのだが、東北と八重山がダイレクトにつながるところが、ついその気にさせられる。
東北は、風車の本場。ナマハゲとパーントゥなどの類似は、しばしば指摘されている。
改めて調べてみたら、サンは首里城のミュージアムショップ球陽でも売っている。
「沖縄に昔からある魔よけ、お守り」というのが、その説明文。
ここで見たのが印象に残っていたのかもしれない・・・
それから・・・
気になっているのは、「沖縄の青」HP(?)の、「天国のない島」という詩。
4年前に双葉社から出た『沖縄人解体真書 ザ・ウチナーンチュ』の文庫版だ。
「ウチナーンチュ丸裸」というサブタイトルが、オクテな探偵団にはちょいと赤面ものなのだが(変?)
持ってきたのは・・・
うーむ。いま試験中だから記事リンクしないでおく。沖縄本ばかり読んでないで、しっかり勉強しなさいね。・・・オレもだな。

その中に、「サン」があった。
こんな説明。
旧暦8月は魔物が多い月といわれ、9~13日に桑の小枝とススキを束ねたサンを家の角や門などに差し、魔物の進入を防ぐ。また、その時期に限らず、サンは料理の上にのせたりもします。
『沖縄人解体真書』はもちろん愛読書のひとつだから、もう何度か読んだはずなのに。すっかり忘れ果てていた。
「家の角や門などに差」すのであれば、これはまったく内地の、ヒイラギに刺したイワシの頭と一緒だ。
(おまけに今が、ちょうどその節分!)
魔除けのヒイラギが、中世ヨーロッパでも同じはたらきをしたことは有名。
「サン(サングヮー)」も、『沖縄人解体真書』(『沖縄学』)の記述だと、むしろ旧暦8月の門飾りにその起源があり、食事などに乗せるのは、そこからの(つまり魔除け、厄除け)からの派生型であると読み取れる。
家に帰って「沖縄・八重山探偵団」を見ると、源氏パイさんのコメントがあった。
ずいぶん放置してしまったのは、月末締め切りの原稿で首が回らなかったから。スミマセン。ぐるぐる。
源氏パイ説では、「藁算」から来ているのではないかという。
形態の類似を鋭くとらえた、さすがに画家ならではの卓見だ。
藁算は、竹富島の喜宝院蒐集館が有名。インカ帝国の縄文字と結びつけられたりもする。
「算」と書いたのは、(詳しく書かずに言うのは気が引けるが)そのイメージがあったから。
ただ、数字や文字を記録するための技術と魔除けとが、どうしても結びつかなかった。
ぼくは竹富島に行ったことがないので(「しきた盆」と呼ばれるその姿は、石垣島から何度も眺めたのだが)、喜宝院蒐集館にも当然行ったことがない。
だから、イメージにあったのは、首里の県立博物館にある民具としてのワラ製玩具だった。
玩具であれば、魔除けとは直結する。
というより、むしろ多くの玩具は、魔除けが変化したものだというのは民俗学の通説だ。
すぐに思い浮かぶのは、やはり八重山のカジマヤー(風車)。
内地でいえば、獅子頭、それから鈴、トラの張り子・・・。
『沖縄学』を持ってきた、試験中の人は、「依り代(ヨリシロ)」だと言い張る。
つまり、漂う霊を閉じ込めるためのシンプルな装置。
これもかなり納得した(ふだんは、あまり納得しないのだが)。
そう言われて思い出したのは、東北地方のオシラサマ。
玩具であり、魔除けである。
地域によって、さまざまな形があるが、頭(カシラ)があるということだけは一致している。
ぼくには、サンの結び目が、頭に見えるのだ。(それは、あるいはジーファーの形態にもかかわっていると思っている)
そもそも「人形」が、もともとは「ヒトガタ」、つまりヨリシロであり魔除けであった。
だから、「依り代」という意見にも納得した。
そして何よりも、「結ぶ」ことによって霊を閉じ込めたり、あるいは強い力を生み出す、そのシンプルな「結ぶ力」への信頼が、サン(サングヮー)からは感じられる。
「縄文」というマジカル・ワードですべて納得した気にはなりたくないのだが、東北と八重山がダイレクトにつながるところが、ついその気にさせられる。
東北は、風車の本場。ナマハゲとパーントゥなどの類似は、しばしば指摘されている。
改めて調べてみたら、サンは首里城のミュージアムショップ球陽でも売っている。
「沖縄に昔からある魔よけ、お守り」というのが、その説明文。
ここで見たのが印象に残っていたのかもしれない・・・
それから・・・
気になっているのは、「沖縄の青」HP(?)の、「天国のない島」という詩。
Posted by び ん at 03:55│Comments(10)
この記事へのトラックバック
以前にもご紹介したことが ありますが・・・ 「サン」です ススキなどの草でくるっと くびったもの。 夜道を歩くときや子供に結んであげて やなむん(お化け)から身を守っ...
沖縄のお守り【南の島のクルク民】at 2008年01月28日 11:27
この記事へのコメント
玩具、ジーファー、、、、魔除け、ナルホドという感じです。
いろいろな地域に類似した魔除け、お守りがあるのですね。
勉強になります。
いろいろな地域に類似した魔除け、お守りがあるのですね。
勉強になります。
Posted by 源氏パイ at 2006年02月02日 07:47
依り代…ほぉ~
つまり、キャッチャーだったと!?
つまり、キャッチャーだったと!?
Posted by pyo at 2006年02月02日 13:14
サーとサンでいっしょに考えたほうがわかりやすい。
「SIRとSAN」英語にすると尊称と聖という意味になり、およそ同じ内容といってもかまわない。サー高なのだから宗教的感性が高い人のことでサーのエナジーを読める人のことです。中国語では察が音として明察が意味として近い。見えないものを観る力です。サンとなるとより「動き」がある状態を指している。異様な力が作動した気配です。沖縄の動詞が「ン」でおわる事を考えたらいい。サンがサイとなるとセーとなりセーファウタキとなる。サイファとは払う力のある場のことだが、あとは顕現するかどうかだ。セーファはショッキングブルー、中島みゆきがとらえた「とてつもない事」が顕現しオーの舞台になるのか?サンニンが強い匂いとたくましい生命力をみこまれてその葉をカーサ「包む」に使う。防腐剤の成分があることは科学的に証明された。作家の吉行氏は払う力があったので、情事は盛んでも顔がうす汚れることはなかった。払う力は彼の場合は夢のかけ橋を純に思い「女の大陸」への接近術を体得したことにあるのであろう。簪のサは挿すのさなのだがカンが微妙な音だ。カンはハンになっても問題はないのだが、ここが難しい。髪サスがカンザシ?髪結はカンユイとは言わないのでサがミをンにさせるのかというと上座はカンザとも一般にはいわないし、反って「ン」が連濁を呼んでサがザになった感がある。カンナビのカンなのだろう。かんを神とするとややこしくなるのでカンとしておきます。方言では髪はカラジだ。KとHは難しい。フミ、ホーラ「米クミ、買おうコーラ」と学校の先生もKがHになる地域のことを面白がって生徒に教えていたことを思い出します。調べてみると以外に広い地域にわたっている。ここでちょっとKの古巣はTWでもあることをいわなければいけません。アマミのキヨラ「清ら」がなぜか促音キョラとなっているが、このキョラに着目して元は五母音だったということの根拠にしている。しかしキュッキョ「清らかな川」と元はキューであってキョーではありません。キュッキョは薩摩の縮めていう癖をとりいれたものです。大概がテーゲーになるが拍を考慮すると長音回避の薩摩はテゲテゲになり四拍を保った。キューキョー「川ゴー」がキュッキョに変わったのは薩摩武士的緊迫ではないか?アマミのヤマト大和は薩摩軍の駐屯地域です。ネットにあるアマミの音はヤマトの地域の音を中心に編集されているので警戒しなければ「ウチナーの本来」が見えてこない。ただキュラーのラが消えたのは理解しにくい。乙音が本来と考えればTWUがツです。TSUの表記になっているが乙音はWを使う音、WUを中心に発音するこも篭り音です。TWAツァTWIツィTWUツゥがヌルが発声していた音だろう。この音はやがて人々の口にのるとチャ、チ、チュともなった。沖縄ではタ、ティ、トゥが一般音として早く固まったので乙音の展開が揺れ動く。茶はチャかサと読む。チャなら、タと読みそうだがサになっている。サシスは案外チャチチュに近いことがわかる。口蓋チャチチュは喉頭を破裂させたキャキキュにかわる。スラーのS氏がチュラー、キュラーのT,K氏の変化を考えれば三母音だけで説明できる。水の幻想Sから現実化のTになった。シンドゥ、ヒンドゥ、インドゥと発音されるようにSとHは交換可能で又たよりなく母音だけの音にもなる。カンはだからハンともいえるからサンにまでふるさと回帰する。ただ濁音、震える音がそもそもなのではないかとの観測はGからKの流れも重視させる。この場合が神ではないか?課題は多いので思考過程の一端と理解してもらいたい。永久トワはTWUWAツァ、チャーで英語チャーチ地上の永遠の場所教会。方言の意味は「いつも」チャーユー。カティードラルは糧の館。カティムンはより英語の音に近い。サンスクリッド語を研究したら非アーリアからの借用、アフリカレベルの大切な音を研究して沖縄の三母音と比較したら面白そうだ。カラジのジがジーファーのジだろう。カージがカジ、髪となるのか?なりそうもないがここはパスしてNとGが微妙だということを記しておきたい。とても重要なことです。イザナミは正確にはイザナンだと思う。絶えざる流動、底の底にはンが流れている。スサノオとアマテラスの対決は理解するのは難しいので民族神ではないイザナで括れば、固めたいギーはンーの合流でギン、ンギとなる。世界の音は銀なのだ。ギン、あるいはジン「中国の仁かもしれない」ンギ、ンジから日本の三貴神は生まれたことになる。ンギのNとGの交錯は仁をジン、ニン、銀をギン、ナン「本島」ニン、ニー「ヤイマ?当て字なのか不明ただニライをギライともいう」語頭のNを喉頭閉鎖音だとしているが、喉頭閉鎖音はMでも同じ音です。すると手話の接点にもなっている音ではないか?手話の使い手はンーという音を響かせながら「お伝えしたいこと」を手話する。文字「アヤ」のない世界、音、外界の音が閉ざされている者はカラダで意思伝達と「ン」の不立文字、以心伝心を表現した。最初のイロハは47文字で「ン」がない。漢字にンから始まる音がないからンを表記しなかったのか、別の暗闘があったのかわからない。しかしそのことが忠臣蔵のトガナクテシスという言霊論につながった。イロハを7文字で行を変え末尾を読むとそうなる。忠君で成り立っている幕藩社会だけに「トガ」の裁量を考えることは当時の社会体制を揺るがしかねない問題だったことはわかる。しかしそれだけだろうか?言霊の雛型だったとはいえないだろうか?「とてつもない事」をみゆきは見誤ったのだろうか?47番目の沖縄県は「ン」にとどまることを重要と考えた文化です。「ン」はさすがに文字化が必要との認識があって後イロハに追加された。「ンート」ヤマトゥンチュだって思考の始まりにはンを使っているのですぞ。ンダ、ナァウワイサ。グブリーサビタン、オロナミン
https://www.mf247.jp/view/index.php?module=rank&g=15
ここで「まいふな」の月明かりが無料ダウンロードできる。
三味線の音がいい。せいいっぱい受けとめたいフィーリング。
「SIRとSAN」英語にすると尊称と聖という意味になり、およそ同じ内容といってもかまわない。サー高なのだから宗教的感性が高い人のことでサーのエナジーを読める人のことです。中国語では察が音として明察が意味として近い。見えないものを観る力です。サンとなるとより「動き」がある状態を指している。異様な力が作動した気配です。沖縄の動詞が「ン」でおわる事を考えたらいい。サンがサイとなるとセーとなりセーファウタキとなる。サイファとは払う力のある場のことだが、あとは顕現するかどうかだ。セーファはショッキングブルー、中島みゆきがとらえた「とてつもない事」が顕現しオーの舞台になるのか?サンニンが強い匂いとたくましい生命力をみこまれてその葉をカーサ「包む」に使う。防腐剤の成分があることは科学的に証明された。作家の吉行氏は払う力があったので、情事は盛んでも顔がうす汚れることはなかった。払う力は彼の場合は夢のかけ橋を純に思い「女の大陸」への接近術を体得したことにあるのであろう。簪のサは挿すのさなのだがカンが微妙な音だ。カンはハンになっても問題はないのだが、ここが難しい。髪サスがカンザシ?髪結はカンユイとは言わないのでサがミをンにさせるのかというと上座はカンザとも一般にはいわないし、反って「ン」が連濁を呼んでサがザになった感がある。カンナビのカンなのだろう。かんを神とするとややこしくなるのでカンとしておきます。方言では髪はカラジだ。KとHは難しい。フミ、ホーラ「米クミ、買おうコーラ」と学校の先生もKがHになる地域のことを面白がって生徒に教えていたことを思い出します。調べてみると以外に広い地域にわたっている。ここでちょっとKの古巣はTWでもあることをいわなければいけません。アマミのキヨラ「清ら」がなぜか促音キョラとなっているが、このキョラに着目して元は五母音だったということの根拠にしている。しかしキュッキョ「清らかな川」と元はキューであってキョーではありません。キュッキョは薩摩の縮めていう癖をとりいれたものです。大概がテーゲーになるが拍を考慮すると長音回避の薩摩はテゲテゲになり四拍を保った。キューキョー「川ゴー」がキュッキョに変わったのは薩摩武士的緊迫ではないか?アマミのヤマト大和は薩摩軍の駐屯地域です。ネットにあるアマミの音はヤマトの地域の音を中心に編集されているので警戒しなければ「ウチナーの本来」が見えてこない。ただキュラーのラが消えたのは理解しにくい。乙音が本来と考えればTWUがツです。TSUの表記になっているが乙音はWを使う音、WUを中心に発音するこも篭り音です。TWAツァTWIツィTWUツゥがヌルが発声していた音だろう。この音はやがて人々の口にのるとチャ、チ、チュともなった。沖縄ではタ、ティ、トゥが一般音として早く固まったので乙音の展開が揺れ動く。茶はチャかサと読む。チャなら、タと読みそうだがサになっている。サシスは案外チャチチュに近いことがわかる。口蓋チャチチュは喉頭を破裂させたキャキキュにかわる。スラーのS氏がチュラー、キュラーのT,K氏の変化を考えれば三母音だけで説明できる。水の幻想Sから現実化のTになった。シンドゥ、ヒンドゥ、インドゥと発音されるようにSとHは交換可能で又たよりなく母音だけの音にもなる。カンはだからハンともいえるからサンにまでふるさと回帰する。ただ濁音、震える音がそもそもなのではないかとの観測はGからKの流れも重視させる。この場合が神ではないか?課題は多いので思考過程の一端と理解してもらいたい。永久トワはTWUWAツァ、チャーで英語チャーチ地上の永遠の場所教会。方言の意味は「いつも」チャーユー。カティードラルは糧の館。カティムンはより英語の音に近い。サンスクリッド語を研究したら非アーリアからの借用、アフリカレベルの大切な音を研究して沖縄の三母音と比較したら面白そうだ。カラジのジがジーファーのジだろう。カージがカジ、髪となるのか?なりそうもないがここはパスしてNとGが微妙だということを記しておきたい。とても重要なことです。イザナミは正確にはイザナンだと思う。絶えざる流動、底の底にはンが流れている。スサノオとアマテラスの対決は理解するのは難しいので民族神ではないイザナで括れば、固めたいギーはンーの合流でギン、ンギとなる。世界の音は銀なのだ。ギン、あるいはジン「中国の仁かもしれない」ンギ、ンジから日本の三貴神は生まれたことになる。ンギのNとGの交錯は仁をジン、ニン、銀をギン、ナン「本島」ニン、ニー「ヤイマ?当て字なのか不明ただニライをギライともいう」語頭のNを喉頭閉鎖音だとしているが、喉頭閉鎖音はMでも同じ音です。すると手話の接点にもなっている音ではないか?手話の使い手はンーという音を響かせながら「お伝えしたいこと」を手話する。文字「アヤ」のない世界、音、外界の音が閉ざされている者はカラダで意思伝達と「ン」の不立文字、以心伝心を表現した。最初のイロハは47文字で「ン」がない。漢字にンから始まる音がないからンを表記しなかったのか、別の暗闘があったのかわからない。しかしそのことが忠臣蔵のトガナクテシスという言霊論につながった。イロハを7文字で行を変え末尾を読むとそうなる。忠君で成り立っている幕藩社会だけに「トガ」の裁量を考えることは当時の社会体制を揺るがしかねない問題だったことはわかる。しかしそれだけだろうか?言霊の雛型だったとはいえないだろうか?「とてつもない事」をみゆきは見誤ったのだろうか?47番目の沖縄県は「ン」にとどまることを重要と考えた文化です。「ン」はさすがに文字化が必要との認識があって後イロハに追加された。「ンート」ヤマトゥンチュだって思考の始まりにはンを使っているのですぞ。ンダ、ナァウワイサ。グブリーサビタン、オロナミン
https://www.mf247.jp/view/index.php?module=rank&g=15
ここで「まいふな」の月明かりが無料ダウンロードできる。
三味線の音がいい。せいいっぱい受けとめたいフィーリング。
Posted by ガジャン at 2006年02月02日 16:17
>源氏パイさん
きっともっとたくさんあると思うのですが・・・
このくらいしか思いつきませんでした。
ほんとに、勉強させていただいています。
>pyoさん
そうそう。UFOキャッチャー・・・のわけないし。
でも、ピッチャーじゃないでしょ(わけわからん)
>ガジャンさん
力のこもったコメント恐縮です。
が・・・できれば段落をわけていただければ幸い。
サーとセジの関係、さらに「精」とのかかわりには関心があります。
KとH、ゲルマン諸語のようですね。カンとハンは北アジアを思わせます。
『いろは歌の謎』(でしたか?)、久しぶりに思い出しました。
「47番目」の論、斬新であろうかと思います。
きっともっとたくさんあると思うのですが・・・
このくらいしか思いつきませんでした。
ほんとに、勉強させていただいています。
>pyoさん
そうそう。UFOキャッチャー・・・のわけないし。
でも、ピッチャーじゃないでしょ(わけわからん)
>ガジャンさん
力のこもったコメント恐縮です。
が・・・できれば段落をわけていただければ幸い。
サーとセジの関係、さらに「精」とのかかわりには関心があります。
KとH、ゲルマン諸語のようですね。カンとハンは北アジアを思わせます。
『いろは歌の謎』(でしたか?)、久しぶりに思い出しました。
「47番目」の論、斬新であろうかと思います。
Posted by びん at 2006年02月02日 19:51
ためになるブログですね~。
仲村さんファンとして興味深く拝読しました。
仲村さんファンとして興味深く拝読しました。
Posted by 南島中毒 at 2006年02月02日 23:25
ふーむ、なるほど。
勉強になりました。
勉強になりました。
Posted by 仲村清司 at 2006年02月03日 11:16
ガジャンさんの論、、凄いといいますか、、2,3会も見返さないと
なかなか理解が難しいですね。
でも凄く勉強になりますね、、、「ん」からはじまる、、、
今日の豊見城の南国食堂にメニュー「ンブサー」がありました。
やはり本土の方々読むのに苦労するでしょうね!
今日は豊見城の「保栄茂」でのスケッチでした。
時折ここにくるのですが、来るたんびに「びん」さん思い出します。
保栄茂=びんと読むのはご存知と思いますが、行政呼び名もそうだと
思います、、、、でも漢字よりかなが少ないとは、、、どう送りがなつけるんでしょうね、、、
ま~たいしたことではないのですが、、、^^;
なかなか理解が難しいですね。
でも凄く勉強になりますね、、、「ん」からはじまる、、、
今日の豊見城の南国食堂にメニュー「ンブサー」がありました。
やはり本土の方々読むのに苦労するでしょうね!
今日は豊見城の「保栄茂」でのスケッチでした。
時折ここにくるのですが、来るたんびに「びん」さん思い出します。
保栄茂=びんと読むのはご存知と思いますが、行政呼び名もそうだと
思います、、、、でも漢字よりかなが少ないとは、、、どう送りがなつけるんでしょうね、、、
ま~たいしたことではないのですが、、、^^;
Posted by 源氏パイ at 2006年02月03日 16:09
>南島中毒さん
仲村さんファンとして興味深く読んでいただきました(^-^>
そう言っていただけるとうれしいです。
>仲村清司さん
著者直々に、どうもいらっしゃいませ。
内容についても書かせていただかないと、ですね。
>源氏パイさん
いや、ほんとうに凄いです。コメントにとどめておくのがもったいない。
思い出していただいて、ありがとうございます。
かなは、「保」に「び」、「茂」に「ん」でよいのでは?
仲村さんファンとして興味深く読んでいただきました(^-^>
そう言っていただけるとうれしいです。
>仲村清司さん
著者直々に、どうもいらっしゃいませ。
内容についても書かせていただかないと、ですね。
>源氏パイさん
いや、ほんとうに凄いです。コメントにとどめておくのがもったいない。
思い出していただいて、ありがとうございます。
かなは、「保」に「び」、「茂」に「ん」でよいのでは?
Posted by びん at 2006年02月03日 18:07
保栄茂を「びん」と読ませるに至った経緯、
たしか宮古にいった時、飛行機の機内誌で読んだ記憶が…。
たしか宮古にいった時、飛行機の機内誌で読んだ記憶が…。
Posted by pyo at 2006年02月03日 19:52
宮古便といえばANA?JTA? で、いつですかぁ?
ぼくも前に調べたけど、3つほど説のあった記憶が・・・。
ぼくも前に調べたけど、3つほど説のあった記憶が・・・。
Posted by びん at 2006年02月04日 00:27
お返事が遅くなる場合があります。あしからず。