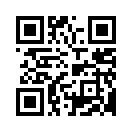2006年01月30日
サン(サングワー)のこと
少し前、源氏パイさんの「今日の風景」で、サン(サングワー)が話題となった。
かつてpyoさんの「なんくる主婦の年中わーばぐち」で、シーミーの時に重箱の上に乗せると書いていたのを、うっすらと覚えていた。
で・・・いつものごとく、気になってしまった。
「サン」は、なんだろう?
桟? 山? 珊? 傘? 算?・・・
いろいろ考えられる。
ひょっとして「簪(さん)」ではないのだろうか?
訓読みすれば、かんざし。
「算」や「桟」という可能性も考えられるが、以下のように考えれば「簪」が適当ではないか。
源氏パイさんのところで、teasdecafさんがコメントしている。
7年ほど前、私に相当年の離れた従兄弟ができたとき、
その子を預かったのですが、泣きやまない事が多かったので
母が、その敷き布団の下に、ケースに入った果物ナイフと、このサンを入れてました。
果物ナイフは危ないだろう??と思ってたのですが、
魔よけなんですね。
かんざしというのは、もともと身を守るナイフ(元々は懐刀)と同じ役割をするのだ。
つまり、魔除け。
沖縄では、よく知られているように、簪のことを「ジーファー」という。
が、これは装飾品としての呼び名なので、魔除けとしては「サン」と呼ばれたものと考えておきたい。
本来は、簪(かんざし)の形であったものが、草や葉でつくられるようになった。
金属のままでは貴重でもあるし、危険でもあるから。
そんなことを考えた。
でも、ちょっと自信がない。
「サン」が「かんざし」を模したものだとして、なぜ「ジーファー」と呼ばなかったか。
そこのところが説明できないからだ。
ずっと「下書き」にしていたのだけれど、UPしてみる。
どなたか、「サン(サングワー)」の語源、ご存じないですか?
かつてpyoさんの「なんくる主婦の年中わーばぐち」で、シーミーの時に重箱の上に乗せると書いていたのを、うっすらと覚えていた。
で・・・いつものごとく、気になってしまった。
「サン」は、なんだろう?
桟? 山? 珊? 傘? 算?・・・
いろいろ考えられる。
ひょっとして「簪(さん)」ではないのだろうか?
訓読みすれば、かんざし。
「算」や「桟」という可能性も考えられるが、以下のように考えれば「簪」が適当ではないか。
源氏パイさんのところで、teasdecafさんがコメントしている。
7年ほど前、私に相当年の離れた従兄弟ができたとき、
その子を預かったのですが、泣きやまない事が多かったので
母が、その敷き布団の下に、ケースに入った果物ナイフと、このサンを入れてました。
果物ナイフは危ないだろう??と思ってたのですが、
魔よけなんですね。
かんざしというのは、もともと身を守るナイフ(元々は懐刀)と同じ役割をするのだ。
つまり、魔除け。
沖縄では、よく知られているように、簪のことを「ジーファー」という。
が、これは装飾品としての呼び名なので、魔除けとしては「サン」と呼ばれたものと考えておきたい。
本来は、簪(かんざし)の形であったものが、草や葉でつくられるようになった。
金属のままでは貴重でもあるし、危険でもあるから。
そんなことを考えた。
でも、ちょっと自信がない。
「サン」が「かんざし」を模したものだとして、なぜ「ジーファー」と呼ばなかったか。
そこのところが説明できないからだ。
ずっと「下書き」にしていたのだけれど、UPしてみる。
どなたか、「サン(サングワー)」の語源、ご存じないですか?
Posted by び ん at 18:15│Comments(5)
この記事へのトラックバック
以前にもご紹介したことが ありますが・・・ 「サン」です ススキなどの草でくるっと くびったもの。 夜道を歩くときや子供に結んであげて やなむん(お化け)から身を守っ...
沖縄のお守り【南の島のクルク民】at 2008年01月28日 11:26
この記事へのコメント
ふーむ。
RIKのKUWAさんあたりに調べてもらいたい話題かも?
RIKのKUWAさんあたりに調べてもらいたい話題かも?
Posted by pyo at 2006年01月30日 18:39
こんばんは びんさん。
なるほど、サンにはそういう意味があったんですね。
かんざし=魔よけとは。 それがサンに変わっている
というのはおもしろいですね。
子どもが七五三で着る着物の装飾品で
守り刀を脇にさしておく事を思い出しました。懐剣っていうんですね。
なるほど、サンにはそういう意味があったんですね。
かんざし=魔よけとは。 それがサンに変わっている
というのはおもしろいですね。
子どもが七五三で着る着物の装飾品で
守り刀を脇にさしておく事を思い出しました。懐剣っていうんですね。
Posted by teasdecaf at 2006年01月30日 22:37
>pyoさん
お願いします!
RIKのKUWAさんでも
SASのKUWATAさんでも、かまいませんので(^-^д
>teasdecafさん
いえ、ほんとはどうなのか、わからないのです。
ちょっと自分なりに考えてみた、というだけで・・・
女性の守り刀って、とてもポピュラーでしたよね。
「懐剣」の情報も、ありがとうございます!
お願いします!
RIKのKUWAさんでも
SASのKUWATAさんでも、かまいませんので(^-^д
>teasdecafさん
いえ、ほんとはどうなのか、わからないのです。
ちょっと自分なりに考えてみた、というだけで・・・
女性の守り刀って、とてもポピュラーでしたよね。
「懐剣」の情報も、ありがとうございます!
Posted by びん at 2006年01月31日 04:14
昔、藁算(ワラザン)というのが、琉球王府時代にあり。
当時それでもって計算や文字の代わりをしていた、、、
其の辺りからきたのではと思いますが、、、、?
形は近いのがあります。
博物館で民芸品と一緒に見たことありますが???
当時それでもって計算や文字の代わりをしていた、、、
其の辺りからきたのではと思いますが、、、、?
形は近いのがあります。
博物館で民芸品と一緒に見たことありますが???
Posted by 源氏パイ at 2006年01月31日 14:12
ありがとうございます。
ワラザン、念頭にありました。
おそらく根を同じくする玩具とともに。
ただ、民具の除厄性というのは考えませんでした。
・・・そうなると、「算」でいいのでしょうか?
ワラザン、念頭にありました。
おそらく根を同じくする玩具とともに。
ただ、民具の除厄性というのは考えませんでした。
・・・そうなると、「算」でいいのでしょうか?
Posted by びん at 2006年02月02日 01:34
お返事が遅くなる場合があります。あしからず。