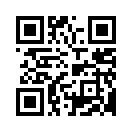2017年06月04日
「沖縄の中南部にはなぜカラスが少ないのか」 再論 (その序に代えて)
このところ鳥の話ばかり書いて、思い出したことがある。
今からちょうど10年前(2007年6月)のこと、
国際通り沿いにあるホテルに泊まって、
朝早く起きて、周辺を相当くまなく散策した。
(出会ったのは、たくさんの猫、そして鳥。)
それらは、「国際通りの朝の顔」と題して、
その後、しばらくたって連続記事にまとめた。
その中でも、第7回目に書いた、
「沖縄の中南部にはなぜカラスが少ないのか」
という記事には、ありがたいことに今でもアクセスが多く、
アクセス解析を見ると、2200余りがカウントされている。
(先ほど見た時点でのカウント数は、2233アクセス)
こんな記事・・・。
(リンクは、後述の通り、ほとんど切れています。)

『(国際通りの周辺で)
「わがもの顔」なのは、ハト。
カラスの少なさは、特記もの。
(内地では、この時間に、このような場所にいるのは、ほぼ間違いなくカラス)
沖縄(とくに中南部)にカラスがいない(少ない)ことについて、いくつか記事リンク。
http://www.rik.ne.jp/oki-byou/sub18.html
http://www.inforoot.jp/okinawa21/index.php?ID=91
http://www16.ocn.ne.jp/~gajimaru/23/page234.html
http://homepage2.nifty.com/qwe00211/okinawa1.htm
なぜ、中南部にカラスが少ないのか・・・
北部で十分生活して行けるからではないかと思う。
(逆に、北部でのカラス被害は、相当なもののようだ)
http://okiguns.blog.ocn.ne.jp/obihirobukai/2007/06/post_574f.html
ちなみに、新城島の民話に登場するカラス。
スーちゃんの妖怪通信「疫病を運ぶヨーラー(夜烏)」
こちらは、かなりおもしろい「カラス研究室」。
http://homepage3.nifty.com/shibalabo/crow/ 』(引用終わり)
ただし、2007年から10年たってみると、
すでに、「スーちゃんの妖怪通信」以外のリンク先は、
いずれも「ページが見つかりません」の状態になっている。
そもそも、読んでもらえるほどの情報のある記事ではなく、
そのうえ、リンク先も開かないというのであれば意味がない。
「カラスがなぜ少ないのか」を知りたくてアクセスしたものの、
役に立つことが何も書いてないので、すぐに遷移してゆく、
そんな大量の通過の対象であるのは、なさけない。
(この記事に、それほどニーズがあるとは思わなかった。
ほかに、もっと読んでもらえる記事は、たぶんあるのだけれど・・・。)
そのことが、多少なりとも気になっていたので、
今年になって、上の記事に追記を記した。(5月27日)
『なお、2015年6月・10月、2016年3月・6月と、
短期間に続けて国際通りを訪れる機会があり、
今でもやはりカラスの数は少ないと感じました。
夜中に残飯等のゴミ出しをしない、などといった、
社会的な衛生面でのモラル順守が進んでいることや、
国際通り周辺に棲む猫の数が非常に多いことなど、
(とはいえ各地で猫はカラスに蹂躙されていますが)
それなりの事情があるのだと、理解しています。
この記事、2200以上のアクセスがあって、
多くの人が読んでくださっているため、
リンク先がことごとく読めなくなっていることが、
とても気になっていたので、追記しておきます。』
アクセスが少なければ無視したのかと言われれば、
現実的に、そうだったのかもしれないと思うのだけれど、
それでも、鳥のことにかんしては多少は興味があるので、
国際通りのカラスについては、もう一度考えてみたい。
・・・そんなふうに思っていたし、今も思っている。
そして、ぼくなどが拙考するまでもなく、
参照すべき考察の先行事例があれば、
それ(それら)を参照させていただければと思う。
たとえば、沖縄でのカラスの生息数は、
日本本土に比べて、多いのか、少ないのか。
あるいは、沖縄のカラスはどのように分布していて、
どのような生活圏を有しているのか、などなど、
「国際通りのカラス」という「点」を考えるには、
包括的な視点、つまり「面」から知っておくべきことが、
考察の前提条件として、いくらでもあるのだと思う。
ぼくは高2で生物学科への進学をあきらめた人間で、
いまやほぼ完全に文系人間と化しているので、
それらを語るにふさわしい条件は何もない。
それでも、おそらく2000人以上もの人が、
「なぜ国際通りにはカラスが少ないのか」を、
知りたがっていると想定されるのである以上、
(とても中途半端な記事を書いてしまった責任上)、
少なくとも自分で納得できる答えには行き着きたいと思う。
というわけで、6月21日から24日までの間、
できれば2日は朝早く起き、そのうちの1日は、
国際通りの周辺をうろうろしたいと思っている。
昨年すずめと少し話ができるようになったので、
国際通りのすずめに、話を聞いてみようと思って。
(参照:年の瀬に振り返ってみると、今年一番の収穫は、
すずめとコミュニケートできるようになったことかもしれない(笑))
ま、でも、国際通りのすずめたちが、
ウチナーグチで話をしていたならば、
ヒアリングには、少し手間取るでしょうね。
直接カラスに聞いてみるという手もありますが、
たぶん彼らは、ハナから相手にしてくれないでしょう。
というか、カラス語は、ちっともわからないし・・・。
おまけに、国際通りにカラスいないし。
(ちょっと、オチのつけ方に困っています・苦笑)
今からちょうど10年前(2007年6月)のこと、
国際通り沿いにあるホテルに泊まって、
朝早く起きて、周辺を相当くまなく散策した。
(出会ったのは、たくさんの猫、そして鳥。)
それらは、「国際通りの朝の顔」と題して、
その後、しばらくたって連続記事にまとめた。
その中でも、第7回目に書いた、
「沖縄の中南部にはなぜカラスが少ないのか」
という記事には、ありがたいことに今でもアクセスが多く、
アクセス解析を見ると、2200余りがカウントされている。
(先ほど見た時点でのカウント数は、2233アクセス)
こんな記事・・・。
(リンクは、後述の通り、ほとんど切れています。)

『(国際通りの周辺で)
「わがもの顔」なのは、ハト。
カラスの少なさは、特記もの。
(内地では、この時間に、このような場所にいるのは、ほぼ間違いなくカラス)
沖縄(とくに中南部)にカラスがいない(少ない)ことについて、いくつか記事リンク。
http://www.rik.ne.jp/oki-byou/sub18.html
http://www.inforoot.jp/okinawa21/index.php?ID=91
http://www16.ocn.ne.jp/~gajimaru/23/page234.html
http://homepage2.nifty.com/qwe00211/okinawa1.htm
なぜ、中南部にカラスが少ないのか・・・
北部で十分生活して行けるからではないかと思う。
(逆に、北部でのカラス被害は、相当なもののようだ)
http://okiguns.blog.ocn.ne.jp/obihirobukai/2007/06/post_574f.html
ちなみに、新城島の民話に登場するカラス。
スーちゃんの妖怪通信「疫病を運ぶヨーラー(夜烏)」
こちらは、かなりおもしろい「カラス研究室」。
http://homepage3.nifty.com/shibalabo/crow/ 』(引用終わり)
ただし、2007年から10年たってみると、
すでに、「スーちゃんの妖怪通信」以外のリンク先は、
いずれも「ページが見つかりません」の状態になっている。
そもそも、読んでもらえるほどの情報のある記事ではなく、
そのうえ、リンク先も開かないというのであれば意味がない。
「カラスがなぜ少ないのか」を知りたくてアクセスしたものの、
役に立つことが何も書いてないので、すぐに遷移してゆく、
そんな大量の通過の対象であるのは、なさけない。
(この記事に、それほどニーズがあるとは思わなかった。
ほかに、もっと読んでもらえる記事は、たぶんあるのだけれど・・・。)
そのことが、多少なりとも気になっていたので、
今年になって、上の記事に追記を記した。(5月27日)
『なお、2015年6月・10月、2016年3月・6月と、
短期間に続けて国際通りを訪れる機会があり、
今でもやはりカラスの数は少ないと感じました。
夜中に残飯等のゴミ出しをしない、などといった、
社会的な衛生面でのモラル順守が進んでいることや、
国際通り周辺に棲む猫の数が非常に多いことなど、
(とはいえ各地で猫はカラスに蹂躙されていますが)
それなりの事情があるのだと、理解しています。
この記事、2200以上のアクセスがあって、
多くの人が読んでくださっているため、
リンク先がことごとく読めなくなっていることが、
とても気になっていたので、追記しておきます。』
アクセスが少なければ無視したのかと言われれば、
現実的に、そうだったのかもしれないと思うのだけれど、
それでも、鳥のことにかんしては多少は興味があるので、
国際通りのカラスについては、もう一度考えてみたい。
・・・そんなふうに思っていたし、今も思っている。
そして、ぼくなどが拙考するまでもなく、
参照すべき考察の先行事例があれば、
それ(それら)を参照させていただければと思う。
たとえば、沖縄でのカラスの生息数は、
日本本土に比べて、多いのか、少ないのか。
あるいは、沖縄のカラスはどのように分布していて、
どのような生活圏を有しているのか、などなど、
「国際通りのカラス」という「点」を考えるには、
包括的な視点、つまり「面」から知っておくべきことが、
考察の前提条件として、いくらでもあるのだと思う。
ぼくは高2で生物学科への進学をあきらめた人間で、
いまやほぼ完全に文系人間と化しているので、
それらを語るにふさわしい条件は何もない。
それでも、おそらく2000人以上もの人が、
「なぜ国際通りにはカラスが少ないのか」を、
知りたがっていると想定されるのである以上、
(とても中途半端な記事を書いてしまった責任上)、
少なくとも自分で納得できる答えには行き着きたいと思う。
というわけで、6月21日から24日までの間、
できれば2日は朝早く起き、そのうちの1日は、
国際通りの周辺をうろうろしたいと思っている。
昨年すずめと少し話ができるようになったので、
国際通りのすずめに、話を聞いてみようと思って。
(参照:年の瀬に振り返ってみると、今年一番の収穫は、
すずめとコミュニケートできるようになったことかもしれない(笑))
ま、でも、国際通りのすずめたちが、
ウチナーグチで話をしていたならば、
ヒアリングには、少し手間取るでしょうね。
直接カラスに聞いてみるという手もありますが、
たぶん彼らは、ハナから相手にしてくれないでしょう。
というか、カラス語は、ちっともわからないし・・・。
おまけに、国際通りにカラスいないし。
(ちょっと、オチのつけ方に困っています・苦笑)
お返事が遅くなる場合があります。あしからず。