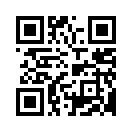2020年12月23日
中央公会堂(大阪中之島)のこと
2つ前の記事に書いたからというわけではないが、
大阪中之島の中央公会堂の近くまで行ってきた。
どうしても読まなければならない本ができたので、
中央公会堂の隣りの中之島図書館に行ったのだ。

(大阪府立中之島図書館。寒くてカメラが傾いている・汗)
いったん入ったら、なかなか出てこないので、
入る前に、隣りの中央公会堂も撮っておいた。

(中之島の南を流れる土佐堀川。図書館や公会堂は左側の木立の奥)
川中島なので、川風がとんでもなく冷たかったし、
はやく図書館に入りたかったので、やや遠方から。

(大阪市中央公会堂)
この建物で、100年前に芥川龍之介が、
そして、沖縄に出発する直前の柳田國男が、
講演をした。あの中之島の中央公会堂である。
(参考:大阪市中央公会堂 施設紹介)
一時は古くなったので取り壊すことに決まったが、
大阪市民の反対運動で、かろうじて生き延びた。
(信じられない話だが、ほんとうのことである。)
当時、大阪維新の市長でなくて本当によかった。
(彼らは中央公会堂に匹敵する数々の文化財を、
この10年のあいだ、次々に破壊し続けてきた。
「生き延びる価値があれば勝手に生き延びる」と、
それこそ勝手な理屈をつけて。冗談じゃない!
為政者の保護がなければ芸能は存在していない。
つまり、吉本もしゃべくり漫才もMー1もなかった。)
それどころか、今や中央公会堂は人気が沸騰し、
大いに「儲かる」ので、予算が大量に投入されて、
どんどん綺麗に、そして便利になっていくのだ。
こういう場当たり的な取捨選択が本当に迷惑。
文化は自分たちが作り出して行くという取組は、
為政者の大事な職掌のひとつではないのか?
ただ、「人気」の方向には、彼らは本当に鼻が利く。
(しかし、幸い「都構想」だけは嗅ぎ分けられず、
しかし「次」がありそうで、全く油断できない。)
じつは、はばかりながら、ぼくも数年前、
ここで、記者会見に臨んだことがある。
とある劇団の大阪公演前の記者会見。
芥川の場合は菊池寛や宇野浩二と一緒に、
大阪毎日新聞の主催講演会であったから、
1100席以上ある大集会室での講演だろう。
この時(1920年)の写真は見たことがないが、
直木三十五の昭和8年(1933)の講演の時は、
大集会室に、ぎゅうぎゅう詰めの写真が残っている。
(参照:モダン周遊「装飾の快楽 <大阪市中央公会堂>」)
もっとも、この頃の直木は日本一人気のあった作家で、
それも大阪は直木の出身地かつホームグラウンドであり、
『直木三十五全集』出版記念の講演会でもあったから、
1100余席を満席にするだけの条件に満ちていた。
この翌年に直木は亡くなってしまうので(享年43)、
大阪を代表する講堂で講演出来てよかったのでは。
これに対して、大正9年の芥川はまだ28歳で、
4年前に「鼻」を夏目漱石に激賞されたことで、
実質的にデビューしてからまだ4年目であった。
3年前に最初の短編集『羅生門』が出版され、
2年前には「蜘蛛の糸」や「地獄変」を書き、
1年前に東京毎日新聞の社員となって、
あの叙情的な「蜜柑」などを書いている。
すでに華々しく活躍する新進作家だったが、
大阪では、まだまだ無名に近い存在だった。
なので500席の中集会室だったかもしれない。
調べても、「中央公会堂で講演をした」までで、
どの部屋(講堂)で講演をしたのがかわからない。
それでも、コーディネーターが直木三十五なので、
150席の小集会室だったとはちょっと思えない。
その芥川の師匠である夏目漱石の講演は、
芥川より9年前の明治44年(1911)のこと。
来年になると、その年からちょうど110年になる。
ただし漱石が講演した頃には、まだ古い建物で、
当時は木造2階建てであったと伝えられている。
(参照:地元で漱石発見コミュの旧中之島公会堂と天王寺公会堂)
ちなみに、明石・和歌山・堺と講演を続けてきた漱石は、
(6日間で4講演! どんだけ過密日程だ、と思う。)
4つめの大阪の講演が終わったあと、入院してしまう。
(それでも最後までやったのは、いかにも漱石らしい。
それも、4講演すべて別々の演題で講演している。
そりゃ、倒れてもおかしくないよな、と好ましく思う。)
大阪市内での1か月の入院生活をもとに書いたのが、
今ではあまり読まれなくなってしまったが、『行人(こうじん)』。
漱石が珍しく大阪を描いた小説。そして和歌山に場面を移す。
妻の自分に対する気持ちを疑った兄(一郎)が、
「妻と旅行に行ってくれ」と弟(二郎)に依頼する。
弟は拒むのだが暴風雨で宿泊を余儀なくされるという、
なんだか2時間ドラマのような設定の長編小説である。
心理描写が絶妙で、読んでいてハラハラ・ドキドキする。
おまけに最終章の「塵労」は、今度は二郎にたのまれて、
兄と旅行を続けている友人Hが一郎の心理を解き明かす。
ちょっと残念なのは、最後が断崖絶壁で終わらないこと。
(だからサスペンスドラマじゃないんだって!笑)
ところで、江戸(東京)から故郷の伊賀上野(三重県)へ、
そして奈良を経て、大阪へと旅をしてきた松尾芭蕉が、
「この道や行人(ゆくひと)なしに秋の暮」と詠んだのは、
1694年9月のこと。漱石の『行人』が刊行されたのは、
それから220年後の1914年(大正3年)のことだった。
漱石の『行人』に芭蕉は登場しないが、いずれも大阪。
入院している漱石は、必ず芭蕉のことを思っただろう。
『行人』には、芭蕉が1694年に越えた山の峠近くに、
トンネルを掘って電車(現在の近鉄奈良線)を通す、
そのトンネル(隧道)工事のようすが描かれている。
ちなみに、漱石が入院していたのは「湯川胃腸病院」。
HPをリンクしたように、現在でも営業を続けている。
のちにノーベル賞を受賞する湯川秀樹(旧姓・小川)が、
『行人』にも描かれる院長湯川玄洋の娘・スミと結婚して、
湯川家の婿養子となったことで、この病院はよく知られている。
幸い漱石は湯川胃腸病院を退院して東京の自宅に帰り、
翌年から、『朝日新聞』に「行人」を連載し始めている。

(中之島図書館、中央ホール上のドーム)
ぼくの場合は、特別室での会見だった。
広さでは大・中の集会室にかなわないが、
内装は、なかなか以上のものであったし、
それよりも何よりも、あの漱石や芥川と、
同じ中央公会堂なのだと思うと感激した。
(それ以来、いつかここで講演をすることが、
わが人生の目標のひとつとなっている。)
とはいえ、その時の会見は一人ではなく、
両側に脚本家と、劇団の代表が座っていた。
参加する報道機関は30以下と予測されていたが、
ふたを開けると、40社が集まってくれたので、
スタッフが慌てて椅子の追加に走っていた。
会見時間も、予定していたより長くなった。
なぜか、こちらへの質問ばかりが続いて、
脚本家には、申しわけないことだった。
(ここに書けば、「ああ、あの」と思う人もいる、
一般社会でも、かなり有名な脚本家である。)
前の記事に書いた劇団四季ほどではないが、
それでも観客動員数は3本の指に入る劇団。
主演の俳優は、その後わが家を訪ねてくれて、
近くのファミレスで、3時間も演劇の話をした。
(俳優もマネジャーも、とても若かったので、
なんとなく、ファミレス行きますか、と・・・。
というか、郊外なので、レストランないんです。)
大阪公演は2度あって、2度とも観劇したが、
場所を変えて観ることで、色々勉強になった。
中央公会堂での講演という目標は、
なんだか雲をつかむような話であるが、
同じ中之島の国際会議場での講演は、
やりたいなと思っているうちに実現した。
それも、幸い1000人収容の大会議室で。
ここは比較的新しいので、これまでに誰が、
講演をしたのかは知らなかったが(今も)。
もちろん願っていれば実現するとは限らないが、
願わなければ、実現に近づかないということは、
たぶん、まちがいのないことなのだろうと思う。
(そんな歌が、ドリカムにあったような気がする。)

(せっかくなので、中之島図書館も目標に入れようかな・笑
ここは講演というより、持っている資料の展示会を。)
そういえば、芥川の講演は100年前の11月、
あくる12月に柳田國男が講演をして旅立った。
柳田が沖縄(那覇港)へと到着する1921年1月は、
廃藩置県によって沖縄が鹿児島藩に編入された、
1871年(明治3年)から、ちょうど50年目。
100年前の沖縄は、琉球王国が滅亡してから、
まだ41年目という、そんな時代の沖縄だった。
100年前の柳田は、まさかそれから25年後に、
沖縄が(そして日本が)アメリカの占領下に入り、
「アメリカ世」が続くことなど想像もしなかっただろう。
2020年という(おそらく)2度とない種類の年の瀬に、
100年前、そして50年前のことを、あれこれ考えている。
大阪中之島の中央公会堂の近くまで行ってきた。
どうしても読まなければならない本ができたので、
中央公会堂の隣りの中之島図書館に行ったのだ。
(大阪府立中之島図書館。寒くてカメラが傾いている・汗)
いったん入ったら、なかなか出てこないので、
入る前に、隣りの中央公会堂も撮っておいた。
(中之島の南を流れる土佐堀川。図書館や公会堂は左側の木立の奥)
川中島なので、川風がとんでもなく冷たかったし、
はやく図書館に入りたかったので、やや遠方から。
(大阪市中央公会堂)
この建物で、100年前に芥川龍之介が、
そして、沖縄に出発する直前の柳田國男が、
講演をした。あの中之島の中央公会堂である。
(参考:大阪市中央公会堂 施設紹介)
一時は古くなったので取り壊すことに決まったが、
大阪市民の反対運動で、かろうじて生き延びた。
(信じられない話だが、ほんとうのことである。)
当時、大阪維新の市長でなくて本当によかった。
(彼らは中央公会堂に匹敵する数々の文化財を、
この10年のあいだ、次々に破壊し続けてきた。
「生き延びる価値があれば勝手に生き延びる」と、
それこそ勝手な理屈をつけて。冗談じゃない!
為政者の保護がなければ芸能は存在していない。
つまり、吉本もしゃべくり漫才もMー1もなかった。)
それどころか、今や中央公会堂は人気が沸騰し、
大いに「儲かる」ので、予算が大量に投入されて、
どんどん綺麗に、そして便利になっていくのだ。
こういう場当たり的な取捨選択が本当に迷惑。
文化は自分たちが作り出して行くという取組は、
為政者の大事な職掌のひとつではないのか?
ただ、「人気」の方向には、彼らは本当に鼻が利く。
(しかし、幸い「都構想」だけは嗅ぎ分けられず、
しかし「次」がありそうで、全く油断できない。)
じつは、はばかりながら、ぼくも数年前、
ここで、記者会見に臨んだことがある。
とある劇団の大阪公演前の記者会見。
芥川の場合は菊池寛や宇野浩二と一緒に、
大阪毎日新聞の主催講演会であったから、
1100席以上ある大集会室での講演だろう。
この時(1920年)の写真は見たことがないが、
直木三十五の昭和8年(1933)の講演の時は、
大集会室に、ぎゅうぎゅう詰めの写真が残っている。
(参照:モダン周遊「装飾の快楽 <大阪市中央公会堂>」)
もっとも、この頃の直木は日本一人気のあった作家で、
それも大阪は直木の出身地かつホームグラウンドであり、
『直木三十五全集』出版記念の講演会でもあったから、
1100余席を満席にするだけの条件に満ちていた。
この翌年に直木は亡くなってしまうので(享年43)、
大阪を代表する講堂で講演出来てよかったのでは。
これに対して、大正9年の芥川はまだ28歳で、
4年前に「鼻」を夏目漱石に激賞されたことで、
実質的にデビューしてからまだ4年目であった。
3年前に最初の短編集『羅生門』が出版され、
2年前には「蜘蛛の糸」や「地獄変」を書き、
1年前に東京毎日新聞の社員となって、
あの叙情的な「蜜柑」などを書いている。
すでに華々しく活躍する新進作家だったが、
大阪では、まだまだ無名に近い存在だった。
なので500席の中集会室だったかもしれない。
調べても、「中央公会堂で講演をした」までで、
どの部屋(講堂)で講演をしたのがかわからない。
それでも、コーディネーターが直木三十五なので、
150席の小集会室だったとはちょっと思えない。
その芥川の師匠である夏目漱石の講演は、
芥川より9年前の明治44年(1911)のこと。
来年になると、その年からちょうど110年になる。
ただし漱石が講演した頃には、まだ古い建物で、
当時は木造2階建てであったと伝えられている。
(参照:地元で漱石発見コミュの旧中之島公会堂と天王寺公会堂)
ちなみに、明石・和歌山・堺と講演を続けてきた漱石は、
(6日間で4講演! どんだけ過密日程だ、と思う。)
4つめの大阪の講演が終わったあと、入院してしまう。
(それでも最後までやったのは、いかにも漱石らしい。
それも、4講演すべて別々の演題で講演している。
そりゃ、倒れてもおかしくないよな、と好ましく思う。)
大阪市内での1か月の入院生活をもとに書いたのが、
今ではあまり読まれなくなってしまったが、『行人(こうじん)』。
漱石が珍しく大阪を描いた小説。そして和歌山に場面を移す。
妻の自分に対する気持ちを疑った兄(一郎)が、
「妻と旅行に行ってくれ」と弟(二郎)に依頼する。
弟は拒むのだが暴風雨で宿泊を余儀なくされるという、
なんだか2時間ドラマのような設定の長編小説である。
心理描写が絶妙で、読んでいてハラハラ・ドキドキする。
おまけに最終章の「塵労」は、今度は二郎にたのまれて、
兄と旅行を続けている友人Hが一郎の心理を解き明かす。
ちょっと残念なのは、最後が断崖絶壁で終わらないこと。
(だからサスペンスドラマじゃないんだって!笑)
ところで、江戸(東京)から故郷の伊賀上野(三重県)へ、
そして奈良を経て、大阪へと旅をしてきた松尾芭蕉が、
「この道や行人(ゆくひと)なしに秋の暮」と詠んだのは、
1694年9月のこと。漱石の『行人』が刊行されたのは、
それから220年後の1914年(大正3年)のことだった。
漱石の『行人』に芭蕉は登場しないが、いずれも大阪。
入院している漱石は、必ず芭蕉のことを思っただろう。
『行人』には、芭蕉が1694年に越えた山の峠近くに、
トンネルを掘って電車(現在の近鉄奈良線)を通す、
そのトンネル(隧道)工事のようすが描かれている。
ちなみに、漱石が入院していたのは「湯川胃腸病院」。
HPをリンクしたように、現在でも営業を続けている。
のちにノーベル賞を受賞する湯川秀樹(旧姓・小川)が、
『行人』にも描かれる院長湯川玄洋の娘・スミと結婚して、
湯川家の婿養子となったことで、この病院はよく知られている。
幸い漱石は湯川胃腸病院を退院して東京の自宅に帰り、
翌年から、『朝日新聞』に「行人」を連載し始めている。
(中之島図書館、中央ホール上のドーム)
ぼくの場合は、特別室での会見だった。
広さでは大・中の集会室にかなわないが、
内装は、なかなか以上のものであったし、
それよりも何よりも、あの漱石や芥川と、
同じ中央公会堂なのだと思うと感激した。
(それ以来、いつかここで講演をすることが、
わが人生の目標のひとつとなっている。)
とはいえ、その時の会見は一人ではなく、
両側に脚本家と、劇団の代表が座っていた。
参加する報道機関は30以下と予測されていたが、
ふたを開けると、40社が集まってくれたので、
スタッフが慌てて椅子の追加に走っていた。
会見時間も、予定していたより長くなった。
なぜか、こちらへの質問ばかりが続いて、
脚本家には、申しわけないことだった。
(ここに書けば、「ああ、あの」と思う人もいる、
一般社会でも、かなり有名な脚本家である。)
前の記事に書いた劇団四季ほどではないが、
それでも観客動員数は3本の指に入る劇団。
主演の俳優は、その後わが家を訪ねてくれて、
近くのファミレスで、3時間も演劇の話をした。
(俳優もマネジャーも、とても若かったので、
なんとなく、ファミレス行きますか、と・・・。
というか、郊外なので、レストランないんです。)
大阪公演は2度あって、2度とも観劇したが、
場所を変えて観ることで、色々勉強になった。
中央公会堂での講演という目標は、
なんだか雲をつかむような話であるが、
同じ中之島の国際会議場での講演は、
やりたいなと思っているうちに実現した。
それも、幸い1000人収容の大会議室で。
ここは比較的新しいので、これまでに誰が、
講演をしたのかは知らなかったが(今も)。
もちろん願っていれば実現するとは限らないが、
願わなければ、実現に近づかないということは、
たぶん、まちがいのないことなのだろうと思う。
(そんな歌が、ドリカムにあったような気がする。)
(せっかくなので、中之島図書館も目標に入れようかな・笑
ここは講演というより、持っている資料の展示会を。)
そういえば、芥川の講演は100年前の11月、
あくる12月に柳田國男が講演をして旅立った。
柳田が沖縄(那覇港)へと到着する1921年1月は、
廃藩置県によって沖縄が鹿児島藩に編入された、
1871年(明治3年)から、ちょうど50年目。
100年前の沖縄は、琉球王国が滅亡してから、
まだ41年目という、そんな時代の沖縄だった。
100年前の柳田は、まさかそれから25年後に、
沖縄が(そして日本が)アメリカの占領下に入り、
「アメリカ世」が続くことなど想像もしなかっただろう。
2020年という(おそらく)2度とない種類の年の瀬に、
100年前、そして50年前のことを、あれこれ考えている。
お返事が遅くなる場合があります。あしからず。