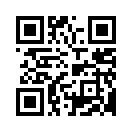2016年05月05日
立夏 立夏 (5月5日に「りっか」という言葉について考えてみた)
今日は、もちろん「こどもの日」であったが、
これは本来、旧暦5月5日の「節」にもとづく。
つまり、陽数(縁起の良い数)である、
1,3,5,7,9が重なる日を貴んで、
古代中国で始まったお祝いの日だ。
今年の旧暦5月5日は6月9日だが、
(で、今日は旧暦の3月29日)
新暦で祝うようになって久しい。
そして、今日は「立夏」でもある。
これは旧暦とはまた別に、
でもやはり古代中国で始まった、
二十四節気という考え方にもとづく。
近年、二十四節気の本がよく売れて、
以前より知る人もはるかに多くなっただろう。

旧暦の1年を24に分割すると、
だいたい一節気が15日前後になる。
そのそれぞれを季節の言葉で呼ぶ。
立夏の次は夏至(今月21日から)であり、
その次は小暑(来月7日から)になる。
立夏は、立春・立秋・立冬と並んで、
比較的よく知られた節気のひとつである。
「夏至」を「夏に至る」と書くので、
夏至が夏が来たという意味かと言えば、
そうではなく、「立夏」がそうなのである。
「立つ」というのは「始まる」という意味。
和歌には「春立つ」という言葉がよく出てくるが、
「夏立つ」という表現は、ほとんど見ない。
春(旧暦の1月~3月)のほうが、
ずっと待ち望まれていたからだろう。
むしろ、出発のことを「出立」と言ったが、
これも「始める」という意味から来ている。
本来、今日1日だけが「立夏」なのではなく、
次の節気までの間がずっと立夏なのだが、
最近は最初の1日だけを呼ぶことが多く、
ニュースでも「今日が立夏です」などと言っている。
「今日から立夏です」が、より正確な言い方である。

沖縄で「りっか」と言えば、たいてい「りっかりっか」と重ねて、
「行こう行こう」と、誘ったりうながしたりする時の言葉である。
本来は、「でぃか、でぃか」のように濁って発音したようだ。
(参照:沖縄方言辞典「リッカ(りっか)」)
大和言葉にも同様に用いられた「いざいざ」という言葉があり、
これは、「いでいで」から来ているものと思われる。
「りっかりっか」。
実際にはあまり聞くことがないのだけれど、
(たぶん、ぼくが旅行者であるからだろう。)
お店の看板などで、時々見かけることがある。
中でも、「りっかりっか湯」は、あいかわらず人気がある。
(参照:Find Travel「ゆんたくあしび湯りっかりっか」)
これは本来、旧暦5月5日の「節」にもとづく。
つまり、陽数(縁起の良い数)である、
1,3,5,7,9が重なる日を貴んで、
古代中国で始まったお祝いの日だ。
今年の旧暦5月5日は6月9日だが、
(で、今日は旧暦の3月29日)
新暦で祝うようになって久しい。
そして、今日は「立夏」でもある。
これは旧暦とはまた別に、
でもやはり古代中国で始まった、
二十四節気という考え方にもとづく。
近年、二十四節気の本がよく売れて、
以前より知る人もはるかに多くなっただろう。
旧暦の1年を24に分割すると、
だいたい一節気が15日前後になる。
そのそれぞれを季節の言葉で呼ぶ。
立夏の次は夏至(今月21日から)であり、
その次は小暑(来月7日から)になる。
立夏は、立春・立秋・立冬と並んで、
比較的よく知られた節気のひとつである。
「夏至」を「夏に至る」と書くので、
夏至が夏が来たという意味かと言えば、
そうではなく、「立夏」がそうなのである。
「立つ」というのは「始まる」という意味。
和歌には「春立つ」という言葉がよく出てくるが、
「夏立つ」という表現は、ほとんど見ない。
春(旧暦の1月~3月)のほうが、
ずっと待ち望まれていたからだろう。
むしろ、出発のことを「出立」と言ったが、
これも「始める」という意味から来ている。
本来、今日1日だけが「立夏」なのではなく、
次の節気までの間がずっと立夏なのだが、
最近は最初の1日だけを呼ぶことが多く、
ニュースでも「今日が立夏です」などと言っている。
「今日から立夏です」が、より正確な言い方である。
沖縄で「りっか」と言えば、たいてい「りっかりっか」と重ねて、
「行こう行こう」と、誘ったりうながしたりする時の言葉である。
本来は、「でぃか、でぃか」のように濁って発音したようだ。
(参照:沖縄方言辞典「リッカ(りっか)」)
大和言葉にも同様に用いられた「いざいざ」という言葉があり、
これは、「いでいで」から来ているものと思われる。
「りっかりっか」。
実際にはあまり聞くことがないのだけれど、
(たぶん、ぼくが旅行者であるからだろう。)
お店の看板などで、時々見かけることがある。
中でも、「りっかりっか湯」は、あいかわらず人気がある。
(参照:Find Travel「ゆんたくあしび湯りっかりっか」)
琉球大学に行きたくて行けなかった昔、
手に入る情報の中で、「温泉」と言えば、
中泊の山田温泉と、りっかりっか湯だった。
今や那覇市内にある銭湯は1つだけだが、
きっとその頃にはいくつも銭湯があったのだろう。
それでもきっと、りっかりっか湯には何度も行ったはず。
今年の3月、那覇セントラルホテルに泊まり、
今は付属施設になっている、りっかりっか湯に入ってきた。
(コーヒー牛乳は高すぎて、買わなかった。)
ずいぶん新しくなったりっかりっか湯であるが、
国際通りから、ほんの一歩裏通りへと入り込むと、
周辺には復帰直後に建てられたような一角があり、
「かつての那覇」を思い浮かべながら、ひとしきり歩ける。
「りっかりっか」と「いざいざ」が本来同じ言葉だなどと言えば、
「ほんまかいな!?」と言われそうであるが、
たぶん正解だと思う。
手に入る情報の中で、「温泉」と言えば、
中泊の山田温泉と、りっかりっか湯だった。
今や那覇市内にある銭湯は1つだけだが、
きっとその頃にはいくつも銭湯があったのだろう。
それでもきっと、りっかりっか湯には何度も行ったはず。
今年の3月、那覇セントラルホテルに泊まり、
今は付属施設になっている、りっかりっか湯に入ってきた。
(コーヒー牛乳は高すぎて、買わなかった。)
ずいぶん新しくなったりっかりっか湯であるが、
国際通りから、ほんの一歩裏通りへと入り込むと、
周辺には復帰直後に建てられたような一角があり、
「かつての那覇」を思い浮かべながら、ひとしきり歩ける。
「りっかりっか」と「いざいざ」が本来同じ言葉だなどと言えば、
「ほんまかいな!?」と言われそうであるが、
たぶん正解だと思う。
お返事が遅くなる場合があります。あしからず。